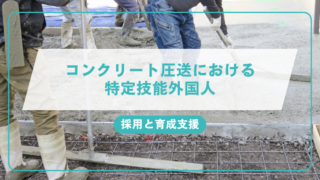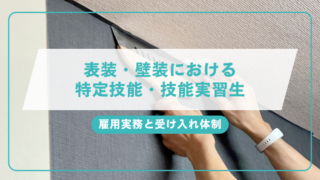介護施設が直面する深刻な人手不足の課題に対し、外国人介護士の採用は有効な解決策となり得ます。介護分野で就労可能な在留資格には「特定技能」「技能実習」「介護」「特定活動(EPA介護福祉士候補者)」などがあり、それぞれの制度の特徴を理解し、適切に運用することで安定した人材確保とサービスの質向上が期待されます。
本記事では、4つの在留資格の比較と選定ポイント、受け入れの流れ、導入メリットや注意点について詳しく解説し、介護施設の運営安定化に貢献する情報をお届けします。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人介護士採用が注目される背景と介護施設の現状
介護業界では人手不足が深刻化しており、介護施設の運営に支障をきたすケースが増えています。そうした中、外国人介護士の採用が有効な解決策として注目されています。制度整備も進みつつあり、現場では人材の確保に加え、職場の多様性向上といった副次的効果も期待されています。
人手不足が深刻化する介護現場の課題
現在、介護業界は慢性的な人材不足に直面しています。特に以下の要因が問題を深刻化させています。
- 高齢化による利用者の増加
- 若年層の介護職離れと担い手不足
- 職場環境や労働条件の厳しさによる離職率の高さ
厚生労働省の調査によれば、今後数十万人単位での介護人材が不足すると予測されており、施設のサービス提供に影響が出ることが懸念されています。
外国人採用がもたらす可能性と現場の変化
外国人介護士の採用により、以下のような効果が期待されています。
- 人材確保による業務負担の軽減
- 多文化環境による職場の活性化
- 特定技能など制度を活用した即戦力人材の確保
一定の日本語力や介護知識を持つ外国人を採用することで、現場の即戦力として活躍が見込めます。また、日本人職員の意識改革やチーム力の向上にもつながるなど、採用効果は業務面だけにとどまりません。ただし、在留資格や文化の違いへの理解と準備は必須です。
外国人採用に活用できる4つの在留資格の違いと選び方
介護人材の確保に向け、外国人を雇用できる制度として代表的な在留資格が4つあります。それぞれに受け入れ要件や就労期間の制限、雇用安定性の違いがあるため、施設の方針や人材戦略に応じて適切な選択が求められます。以下で特徴を整理し、比較表を用いて違いを明確にご紹介します。
特定技能(介護)制度の特徴と採用のしやすさ
特定技能1号(介護)は、外国人が介護職として即戦力として働ける制度です。介護業務に関する技能試験と、日本語能力試験に合格することが前提ですが、比較的採用しやすく、即戦力人材の確保に有効です。
- 雇用期間:最大5年(更新可)
- 永住・家族帯同:不可
- 試験合格が必須
- 技能水準・日本語能力の証明が求められる
特定活動(EPA介護福祉士候補者)の仕組みと受け入れ要件
EPA(経済連携協定)による受け入れは、日本とフィリピン・インドネシア・ベトナムの3国との協定に基づき、国家試験の受験資格を持つ候補者を受け入れる仕組みです。
- 受入れ対象:日本語研修修了者
- 最大4年間の滞在(国家試験合格で在留継続可)
- 合格すれば在留資格「介護」に移行可能
- 制度運用に手間や調整が必要
介護福祉士資格取得による「在留資格・介護」の安定性
在留資格「介護」は、日本の介護福祉士国家試験に合格した外国人に付与される資格で、長期雇用・転職可能・家族帯同可など、最も安定した在留資格です。
- 雇用の自由度が高い
- 在留期間の更新可能、永住申請も視野に
- 資格取得までの支援が必要
技能実習制度における介護職採用の注意点
技能実習制度では、技能移転を目的に介護業務を学びながら就労します。
労働力確保を目的としての採用はできないため注意が必要です。
- 最長就労期間:5年
- 転職不可、事業所変更も原則禁止
- 研修主体のため即戦力性に欠けることも
【比較表】4つの在留資格の主な違い
| 項目 | 特定技能(介護) | 特定活動(EPA介護福祉士候補者) | 在留資格「介護」 | 技能実習(介護) |
| 雇用期間 | 最長5年 | 最大4年(試験合格後更新可) | 5年、3年、1年又は3ヶ月 | 最長5年 |
| 永住・家族帯同 | 不可 | 合格後可能 | 可能 | 不可 |
| 採用しやすさ | 比較的容易 | 制度的ハードルあり | 資格取得が前提 | 受入れ準備に時間がかかる |
| 特徴 | 即戦力、更新制限あり | 国家試験前提、協定国限定 | 安定的雇用が可能 | 技能移転が主目的 |
| 言語要件 | 日本語能力試験N4以上 | 日本語研修修了+N3目安 | 介護福祉士国家試験合格 | N4レベルが目安 |
それぞれの制度にメリット・デメリットがありますので、施設の人材計画や中長期の雇用方針に合わせて選択することが重要です。
採用前に確認すべき要件と採用後の支援体制
外国人介護士を受け入れる際には、在留資格の確認や施設側の体制整備など、採用前後に必要な準備が多岐にわたります。制度ごとに異なる要件や申請書類の確認だけでなく、採用後のサポート体制も整備しておくことで、定着率の向上と職場トラブルの防止につながります。
採用までのステップと必要な申請・届出
外国人介護士を採用するには、在留資格ごとに異なる手続きが必要です。採用前から計画的に準備し、申請の遅れや不備を防ぐことが求められます。
採用前の主な準備事項
- 在留資格の確認(介護、特定技能、EPAなど)
- 日本語能力や介護スキルの確認
- 労働条件通知書や雇用契約書の整備
- 指導員配置や研修制度の確認
- 雇用計画や受け入れ体制の準備
主な申請・届出
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 外国人雇用状況届出書の提出
- 雇用保険・社会保険関連の手続き
在留資格の種類によっては、行政機関との連携や書類審査に数か月かかることもあります。採用スケジュールには余裕を持って進めましょう。
外国人採用の進め方は「外国人採用の進め方と注意点|募集方法・在留資格・支援体制を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
採用後の日本語・生活支援と職場定着サポート
採用後も外国人介護士が安心して働ける環境づくりが必要です。言語や文化の違いに配慮した支援体制を整備することで、職場への定着率やパフォーマンスが向上します。
支援内容の例
- 日本語研修の継続実施(特に介護現場で必要な用語に重点)
- 生活支援(住居、役所手続き、生活インフラの案内)
- 職場でのフォロー体制の強化(定期面談やメンター制度)
- 文化交流・多文化理解の促進(研修やイベントの活用)
特定技能やEPAなど一部の制度では、生活支援の提供が義務化されているため、施設側の責任として具体的な支援計画が求められます。採用はゴールではなくスタートであるという視点で、継続的なサポート体制を構築していきましょう。
外国人採用における日本語力向上の社内教育などについては「外国人採用における日本語レベルと教育支援|業務定着に必要な確認ポイントと対策を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人介護士採用のメリットと導入成功事例
外国人介護士の採用は単なる人材確保の手段ではなく、介護現場に多面的な効果をもたらす取り組みです。多様性を活かしたチームづくりや職員全体のモチベーション向上にもつながり、施設全体の質的向上が期待できます。ここでは、外国人採用によって得られる主なメリットと、実際に成功した国内事例を紹介します。
人材確保だけでない、現場にもたらす3つの効果
外国人介護士の採用によって、施設運営において以下のようなポジティブな変化が見られます。
①安定した人材確保
慢性的な人手不足に悩む介護業界では、安定的な採用ルートとして外国人採用が注目されています。特定技能制度やEPAを活用することで、一定期間の雇用を見込める点も魅力です。
②現場の活性化とチームの多様性
異なる文化背景を持つ人材が加わることで、現場に新しい視点や価値観が生まれ、既存スタッフの刺激にもなります。多様性のある職場づくりは、離職防止や職場満足度の向上にも寄与します。
③サービスの質の向上
外国人介護士は母国での介護経験や医療知識を持つケースも多く、丁寧なケアやホスピタリティの高さが利用者からも好評を得ている事例があります。言葉の壁を越えた温かなケアは、施設の評判向上にもつながります。
定着・活躍につながる運営事例(国内事例あり)
実際に外国人介護士を導入し、成果を上げている介護施設では、受け入れ体制の整備と定着支援の工夫が鍵となっています。
成功事例①:東京都・社会福祉法人A施設
特定技能制度を活用し、フィリピンからの人材を受け入れ。受け入れ前に現地での事前教育と日本語研修を実施し、入職後も定期面談と業務ごとのマニュアルで支援。1年で離職率ゼロを実現。
成功事例②:大阪府・介護付き有料老人ホームB社
EPA候補者を4名受け入れ。国家試験対策に加え、先輩社員との「バディ制度」を導入し、日常業務を通じた実践的な教育を実施。採用から3年後には、2名が介護福祉士に合格しリーダー職に昇格。
成功事例③:地方都市・中規模施設C法人
技能実習制度でベトナム人実習生を受け入れ。宗教や食文化への配慮、生活面でのサポートを強化した結果、現場との信頼関係が構築され、他職員への良い影響も広がった。
このように、単なる採用ではなく「育成・定着・活躍」を見据えた運用が、導入成功の鍵となります。施設ごとのニーズと文化に合った制度選択と、受け入れ体制の強化が重要です。
外国人採用における定着と離職防止は「外国人材の定着と離職防止のポイントを解説|企業が行うべき人事施策について」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
外国人介護士受け入れ時の課題と対策
外国人介護士の受け入れは、介護現場の人材不足を補う有効な手段ですが、現場でのコミュニケーションや制度理解の不十分さが離職やトラブルの原因になることもあります。採用のメリットを活かすためには、受け入れに伴う課題を的確に把握し、事前に対応策を講じることが不可欠です。
コミュニケーション・文化の違いへの対応
外国人介護士との協働において最も多く挙がる課題が、言語の壁と文化の違いです。介護現場では正確な意思疎通が求められるため、日本語能力の不足が業務上のミスやストレスの原因となる場合があります。
このような課題に対する対策としては、以下が有効です。
- 日本語教育の継続支援
入職後も継続的な学習機会を提供し、業務に必要な語彙や表現を重点的に学ばせる。
- 多文化理解研修の実施
日本人職員を対象に、文化的背景の違いへの理解を深める研修を定期的に行う。
- 通訳・多言語ツールの活用
介護記録や研修資料を英語・ベトナム語などで補足するなど、サポート体制を整える。
文化や宗教観の違いによって、食事・生活習慣・人間関係のとらえ方にズレが生じるケースもあります。そのため、施設側が個別の背景を把握し、柔軟な配慮を行う姿勢が重要です。
離職・トラブルを防ぐマネジメントと制度理解
受け入れ初期のフォロー不足や制度の誤解は、早期離職や労使トラブルにつながる大きなリスクです。外国人介護士の受け入れには、以下のような管理と制度理解が不可欠です。
- 業務指導と生活支援を分けて考える
業務面ではマニュアルやOJTを活用して体系的に教える一方、生活面では住宅や通院、買い物支援など日本での生活の不安を軽減する支援が求められます。
- 制度面の誤認識を防ぐための情報提供
特定技能や技能実習制度、EPAなど制度ごとに在留期間や更新条件が異なります。本人だけでなく受け入れ側も制度を正しく理解し、必要な申請や期限を管理することが重要です。
- 定期面談とフォローアップ体制の整備
1on1面談を通じて不安や不満を早期に察知し、必要に応じて配置転換や支援の見直しを行います。これにより、信頼関係の構築と早期離職の防止が可能になります。
マネジメント側が制度的・人的な両面からの受け入れ体制を整えることで、外国人介護士が安心して働ける環境をつくることができるのです。これは最終的に、介護サービスの質と職場全体の安定性にもつながります。
まとめ:介護施設の未来を支える外国人介護士の受け入れ活用
外国人介護士の受け入れは、人手不足に悩む介護施設にとって有効な解決策です。特定技能、EPA、在留資格「介護」、技能実習といった4つの在留資格制度を理解し、施設の状況に合った人材を選ぶことが重要です。
採用には申請手続きや日本語・生活支援、文化的配慮などの体制整備も求められますが、それにより人材の定着と介護の質向上が実現可能となります。介護の現場に多様性を取り入れ、安定した施設運営と職員の負担軽減につなげるためにも、外国人採用は戦略的に活用すべき選択肢です。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/


-640x360.png)