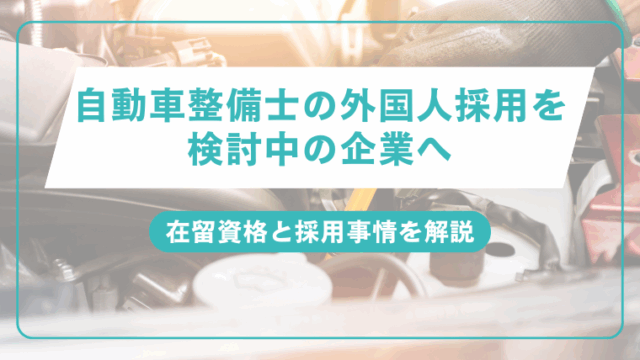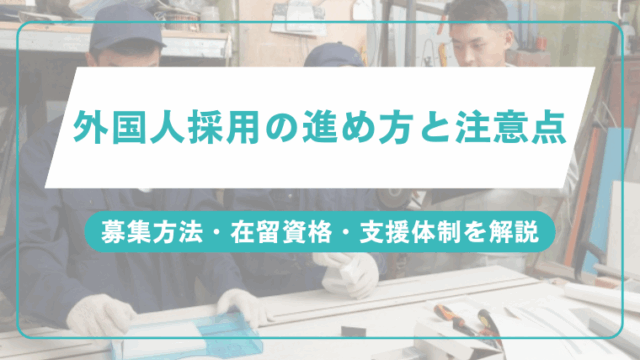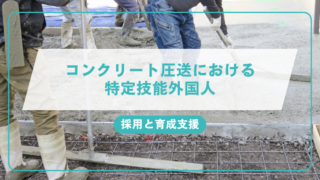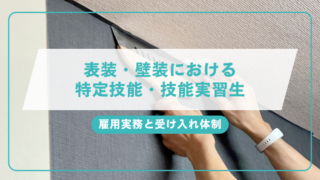外国人を雇用するには、在留資格の確認や必要書類の提出、ハローワークへの届出など、段階ごとの手続きを適切に行うことが重要です。採用後の労務管理や生活支援も含め、対応を誤ると企業のリスクにつながります。
また、手続きを正しく理解しないまま進めると、不法就労や在留資格の不適合といったトラブルを招く可能性もあります。本記事では、スムーズで合法的な外国人採用を実現するための実務ポイントを、採用前から入社後までの流れに沿ってわかりやすく解説します。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人雇用の手続き前に企業が準備すべき3つのチェックポイント
外国人を採用する際には、事前に確認すべき重要なポイントがいくつかあります。特に、在留資格の確認、必要条件の整理、社内体制の整備は、採用後のトラブルを防ぐ上で欠かせません。本章では、この3つのチェックポイントを具体的に解説します。
在留カードで就労可能性を判断する方法
外国人を採用する際に最も基本かつ重要なのが、在留カードの確認です。対象者が日本で合法的に働けるかどうかは、在留資格の種類と就労制限の有無によって判断されます。企業は在留カードの情報を正しく読み取り、業務内容との適合性を確認する必要があります。
確認すべきポイントは以下のとおりです。
- 在留資格の種類(例:技術・人文知識・国際業務、特定技能など)
- 在留期間の有効期限
- 資格外活動許可の有無
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格では、接客や軽作業などの単純労働はできません。また、留学生や家族滞在の資格を持つ人は、資格外活動許可がない限り、アルバイトなどの就労も制限されます。
採用時には、在留カードの両面コピーを取得し、社内で記録・管理する体制を整備しておくことが重要です。業務変更の際にも、在留資格との整合性を再確認し、必要に応じて資格変更手続きを行いましょう。
外国人採用で確認すべきチェックリスト項目
在留資格の確認に加えて、採用に関する準備を体系的に進めるためには、チェックリストの作成と運用が効果的です。必要な項目を事前に明確にしておくことで、書類の漏れや手続きの遅延を防げます。
以下は、採用前に企業が押さえておくべき主な確認事項です。
- 職務内容と在留資格の整合性の確認
- 雇用契約書の作成と母国語訳の準備
- 労働条件通知書・就業規則の整備と説明方法の検討
- 社会保険や雇用保険の加入対象かどうかの確認
- ハローワークへの外国人雇用状況届出の準備
- 日本語能力や社内コミュニケーションの基準設定
チェックリストは、人事部門だけでなく、配属先部門とも共有し、企業全体で採用体制を整えることが大切です。特に初めて外国人を受け入れる企業の場合は、行政書士や専門家と連携して確認体制を強化するのも有効な手段です。
外国人受け入れを支える社内体制の構築ポイント
外国人労働者が円滑に業務を開始し、職場に定着するためには、採用手続きだけでなく受け入れ体制の整備が不可欠です。社内の制度や運用を見直し、文化や言語の違いに対応できる環境を整える必要があります。
社内で整備すべき主なポイントは以下のとおりです。
- 就業マニュアルやルールの多言語化(日本語・英語・母国語など)
- 異文化理解に関する社内研修の実施
- ITツールや通訳の活用による業務支援体制の構築
- 相談窓口の設置や定期的なヒアリングの実施
また、日本人社員に対しても異文化コミュニケーションに関する教育や意識啓発を行うことで、トラブルを防ぎ、チームとしての連携が深まります。外国人採用は、単なる人材補充ではなく、企業文化や価値観を広げる機会でもあります。
採用前から受け入れ体制までを視野に入れて準備することが、外国人雇用の成功の鍵となります。
採用前に行うべき準備と申請手続きの全体像
外国人を採用する際は、雇用契約の締結や各種書類の整備、申請手続きなど、入社前に対応すべき事項が多くあります。手続きの正確さとタイミングの管理が、スムーズな採用の鍵となります。この章では、特に重要な雇用契約書と必要書類の対応について解説します。
雇用契約書の作成ポイントと母国語対応の重要性
外国人と雇用契約を結ぶ際は、契約内容の明確化と外国人本人の理解度を最優先に考える必要があります。特に、言語面での配慮が不十分だと、後に誤解や契約トラブルにつながる可能性があります。
そのため、雇用契約書は日本語と母国語の両言語で作成するのが望ましく、少なくとも本人が十分に理解できるように口頭や翻訳を用いた説明を行う体制を整えましょう。
契約書に盛り込むべき代表的な内容は以下のとおりです。
- 雇用形態(正社員・契約社員・アルバイト等)
- 勤務時間・休日・残業の有無
- 給与額と支払日、昇給・賞与の有無
- 契約期間と更新条件
- 福利厚生、社会保険の適用範囲
- 就業場所と業務内容
特に、外国人労働者の賃金が日本人と同等かつ最低賃金以上であることを明記し、社会保険への加入義務がある場合はその内容も正確に記載しましょう。これは労働基準法や入管法との整合性を保つうえでも重要です。
また、労働条件通知書も併せて発行し、必要に応じて母国語での翻訳を添えて交付することが望ましいです。本人の理解を助けるだけでなく、企業の法的リスクを低減する有効な対策となります。
外国人採用時の雇用契約書について「外国人採用の雇用契約書ガイド|作成時の重要ポイント、注意点を徹底解説!」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
必要書類の一覧と提出タイミングを正しく把握する
外国人を採用する場合、企業は本人から提出を受ける書類だけでなく、企業側が作成・提出すべき書類も多く存在します。それらは、在留資格の種別や採用ルート(国内採用・海外採用)によっても異なりますが、共通して押さえるべき基本項目があります。
採用前後に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 雇用契約書(母国語訳付き)
- 労働条件通知書
- 在留カードのコピー
- 採用予定者の履歴書、学歴証明書
- 会社概要資料(登記簿謄本・直近の決算書など)
- 在留資格認定証明書交付申請書(必要に応じて)
- 外国人雇用状況の届出書(ハローワーク)
- 就労ビザ取得に関する添付資料一式
提出先は入国管理局(出入国在留管理庁)やハローワークなどが主となりますが、タイミングを誤ると審査に時間がかかり、入社が遅れる原因となります。
特に海外から人材を採用する場合は、在留資格認定証明書の交付→ビザ申請→渡航→入国手続き→就労開始というステップがあり、全体で3か月から6か月程度かかることも珍しくありません。
スケジュールに余裕を持ちつつ、必要書類の種類・提出先・提出期限を一覧化して管理することが、ミスや遅延を防ぐポイントです。初めての採用や制度に不安がある場合は、行政書士や人材紹介会社と連携しながら進めるのが安心です。
入社前後に必要な届け出と書類対応の流れ
外国人を採用した場合、雇用契約を締結しただけでは手続きは完了しません。法的に義務付けられている届け出や報告書の提出を、所定の期限内に正確に行う必要があります。特に、ハローワークと入国管理局への対応は見落としやすいため、あらかじめ流れを把握しておくことが重要です。
この章では、入社の前後に企業が行うべき手続きを整理し、それぞれの対応方法と注意点を解説します。
ハローワークへの外国人雇用状況届出の手順
外国人を雇用した企業は、雇用対策法に基づきハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。これは、労働市場の適正な把握と外国人雇用の透明化を目的とした制度で、届け出を怠ると罰則の対象になる可能性もあるため、必ず対応しなければなりません。
届出が必要となる主なケースは以下のとおりです。
- 外国人を新たに雇用したとき
- 外国人が退職したとき
- 契約内容や在留資格に変更があったとき
届け出の際に必要な情報には、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間、在留カード番号、雇用開始日、職務内容などがあります。これらは、企業が在留カード等から正確に転記して提出しなければなりません。
届出は、原則として「雇入れまたは離職の翌月10日まで」に行うことが求められます。手続きはオンラインでも可能ですが、初回や不明点がある場合は、直接ハローワークに相談しながら進めるのが確実です。
外国人を雇用するすべての事業者に義務付けられている手続きであるため、社内ルールとして雇用時に確実に対応できるようフローを整備しておくと安心です。
入国管理局への手続きと提出書類の注意点
外国人の在留資格に関する手続きは、入国管理局(出入国在留管理庁)が管轄しています。特に、在留資格認定証明書の交付申請や在留資格変更・更新手続きは、企業側がサポートすべき重要な業務です。
状況に応じて、以下のような対応が必要となります。
- 新たに外国人を海外から招聘する場合:在留資格認定証明書の申請
- 留学生や家族滞在などからの就労ビザ変更:資格変更申請
- 既存の在留資格が満了する場合:資格更新申請
これらの申請には、以下のような書類が求められます。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書のコピー
- 会社概要資料(登記簿謄本、パンフレットなど)
- 採用者の履歴書・学歴・職歴証明書
- 在留カードの写し
- 理由書(必要に応じて)
審査には通常1か月〜3か月程度かかるため、採用スケジュールに余裕を持って手続きを開始することが求められます。また、申請書類に不備があると差し戻されることもあるため、行政書士など専門家と連携して進めると安心です。
企業が在留資格関連の対応を怠ると、不法就労助長罪などの法的責任を問われる可能性があります。常に最新の入管法と在留資格制度を把握し、確実に手続きを行う社内体制の整備が不可欠です。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
在留資格の取得・更新・変更に関する具体的な対応方法
外国人を正式に雇用するには、対象者が就労可能な在留資格を持っているか、または適切な手続きを通じて取得・変更していることが前提となります。在留資格の内容によって働ける職種や期間が決まっているため、企業は採用時や勤務中において、資格の有効性や適合性を継続的に管理しなければなりません。
この章では、在留資格の新規取得(認定証明書交付申請)、および変更・更新手続きについて、それぞれの手順や注意点を解説します。
在留資格認定証明書の申請手順と必要書類
海外在住の外国人を採用する場合、まず行うべきは「在留資格認定証明書」の交付申請です。これは、外国人が日本に入国・就労するための前提となるビザを取得するために必要な書類であり、企業側が申請主体となるケースが一般的です。
申請の基本的な流れは以下のとおりです。
- 必要書類の収集・準備
- 出入国在留管理庁への申請書類提出
- 証明書の審査・交付(通常1〜3か月)
- 外国人本人が日本大使館でビザ申請
- 入国・在留カード交付・就労開始
主な必要書類は次の通りです。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(業務内容・労働条件が明記されたもの)
- 会社概要資料(登記簿謄本、決算書など)
- 本人の履歴書・学歴証明書・職歴書類
- 在職証明書(職歴がある場合)
- パスポートのコピー
- 理由書(任意だが提出推奨)
特定技能などの資格では、技能試験の合格証明書や日本語能力の証明も必要となります。書類に不備があると審査が大幅に遅れるため、事前に内容を精査し、行政書士など専門家に相談するのが安全です。
なお、証明書の交付後に本人が入国するまでの間に、就労条件が変わった場合は再申請が必要になることもありますので、入社日が確定してから申請を行うのが理想的です。
在留資格変更・更新の進め方と期限管理の注意
外国人がすでに日本に在留している場合でも、在留資格が現在の業務内容に適していなければ就労はできません。たとえば、「留学」や「家族滞在」の在留資格では原則として就労が認められていないため、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザに変更する必要があります。
また、すでに就労可能な在留資格を持っている場合でも、在留期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
変更・更新手続きの流れは以下のとおりです。
- 本人が最寄りの入国管理局で申請手続き
- 必要書類を提出(変更・更新のどちらも類似)
- 審査期間(1〜2か月程度)を経て許可
- 新しい在留カードの受け取り
変更・更新時に必要となる代表的な書類は次の通りです。
- 在留資格変更許可申請書/在留期間更新許可申請書
- 雇用契約書
- 会社の登記簿謄本・決算書などの会社概要資料
- 本人の在留カードのコピー、パスポートのコピー
- 労働条件通知書・源泉徴収票(必要に応じて)
申請のタイミングも非常に重要です。更新は在留期限の3か月前から申請可能となりますが、ギリギリになると許可が下りる前に在留期限を迎えてしまう恐れがあります。そのため、社内で在留期限の管理体制を構築し、定期的に対象者のステータスを確認する必要があります。
資格変更が必要になるのは、以下のようなケースです。
- 留学生から新卒採用で正社員になる場合
- 在留資格「家族滞在」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更する場合
- 職種が変更となり、現在の資格では対応できない場合
在留資格の維持・管理は、企業の義務ではないものの、実質的には企業の責任として機能している場面が多いため、担当部門で一元管理を行うとトラブルを未然に防げます。
採用後のサポートと社会保険・労務管理の留意点
外国人を採用したあとは、法定手続きだけでなく、職場への定着支援も重要です。保険加入や労務管理の正確な対応と、生活支援の工夫を通じて、安定した雇用環境を整えることが求められます。
社会保険・労災・雇用保険の加入手続き
外国人であっても、日本の労働者として雇用される場合は、原則として社会保険や労災保険、雇用保険の対象となります。企業は日本人社員と同様に、必要な手続きを期限内に行う義務があります。
加入対象となる保険は次の通りです。
- 健康保険・厚生年金保険:所定の労働時間と期間を満たす場合は加入義務あり
- 雇用保険:週20時間以上勤務し、31日以上の雇用見込みがある場合に適用
- 労災保険:すべての労働者に適用(雇用形態・国籍を問わず)
手続きの主な流れは以下のとおりです。
- 採用時に在留カード・マイナンバーを確認
- 所轄の年金事務所・ハローワークに加入申請
- 健康保険証の交付、雇用保険被保険者証の発行
- 賃金台帳や出勤簿への記載、保険料の天引き・納付
留意点として、在留資格の有無は保険加入の可否には直接影響しません。労働者として雇用されているかどうかが判断基準となるため、短期滞在であっても条件を満たせば加入義務が発生します。
適切な手続きを怠ると、未加入による行政指導や、本人の保険給付が受けられないといった不利益が生じるため、採用と同時に保険対応を進める体制を整備しておくことが必要です。
外国人雇用時の雇用保険については「外国人雇用における雇用保険手続き、日本人との違いと重要ポイント解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
外国人が職場に定着するための生活支援の工夫
外国人が安心して働き続けるには、業務面だけでなく生活全般へのサポートも非常に重要です。特に、来日間もない人材にとっては、住居、銀行口座、携帯電話、公共サービスなど、日常生活に関わるサポートが不可欠です。
企業が取り組むべき主な支援内容は以下のとおりです。
- 住居の確保や契約手続きのサポート(保証人代行や賃貸住宅の紹介など)
- 銀行口座・携帯電話契約の手続き支援
- 生活必需品の準備や地域の情報提供
- 日本語学習の支援や通訳の配置
- 社内ルールやビジネスマナーに関する研修の実施
定着率を高めるには、定期的な面談によるフォローアップが効果的です。職場や生活面の悩みを早期に把握し、必要に応じて社内で支援を行う体制を整えましょう。
また、社内イベントや交流機会の提供により、日本人社員との文化的ギャップを埋め、相互理解やチームワークの向上を促すことができます。
採用後のサポートは、長期的な雇用関係の鍵となるため、生活支援と労務管理の両面から取り組むことが重要です。
外国人採用における定着と離職防止は「外国人材の定着と離職防止のポイントを解説|企業が行うべき人事施策について」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
外国人採用手続きを円滑にするための実務チェックリスト
外国人を雇用する際は、手続きの多さと煩雑さから、社内体制と情報管理の整備が欠かせません。トラブルを防ぐには、事前の確認と標準化された運用ルールが重要です。
企業が整備すべき社内体制と書類管理方法
採用から就労開始までのミスを防ぐには、社内の連携体制と書類管理の仕組みを明確にしておく必要があります。特に人事・労務・配属先間での情報共有は重要です。
以下の項目は、採用体制を整える上での基本です。
- 採用フローや申請手続きのマニュアル化
- 在留カードや契約書の保管・期限管理のルール化
- 在留資格の満了日を一括管理する台帳の整備
- 多言語対応や通訳支援の体制づくり
- 部署間の役割分担の明確化と共有
これらの体制がないと、提出漏れや資格管理ミスが起こりやすくなり、企業の責任を問われるリスクも高まります。採用情報を一元管理できるツールの活用も有効です。
トラブルを未然に防ぐための運用ルールと対応例
外国人雇用では、文化・制度・言語の違いからさまざまな誤解やトラブルが発生しがちです。代表的なリスクとその予防策は以下の通りです。
| トラブル例 | 主な原因 | 予防策 |
| 業務が在留資格に適合しない | 配属ミス | 事前に在留カードと業務の適合性を確認 |
| 労働条件の誤解 | 説明不足 | 契約書の翻訳・丁寧な説明の実施 |
| 日本語不足によるミス | 能力把握不足 | 面接時の日本語確認と研修実施 |
| 職場での摩擦 | 異文化ギャップ | 異文化理解研修や交流の機会を設ける |
また、相談窓口の設置やマニュアルの整備によって、トラブル発生時にも迅速に対応できます。現場でも活用できるよう、対応フローや想定問答集を用意しておくと安心です。
まとめ:外国人採用の手続きを成功させるために押さえるべきポイント
外国人採用を円滑に進めるには、在留資格の確認から雇用契約書の作成、必要書類の提出、社会保険の加入に至るまで、各手続きの流れを正確に把握し、社内での管理体制を整えることが重要です。
また、外国人労働者の生活支援や異文化対応も定着率の向上に欠かせません。ハローワークや入国管理局への届け出・申請のタイミングを守り、法令遵守を徹底することで、トラブルやリスクを未然に防ぐことができます。
手続きの全体像を把握し、部門間で役割分担と情報共有を行うことが、企業の持続的な人材活用につながります。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/