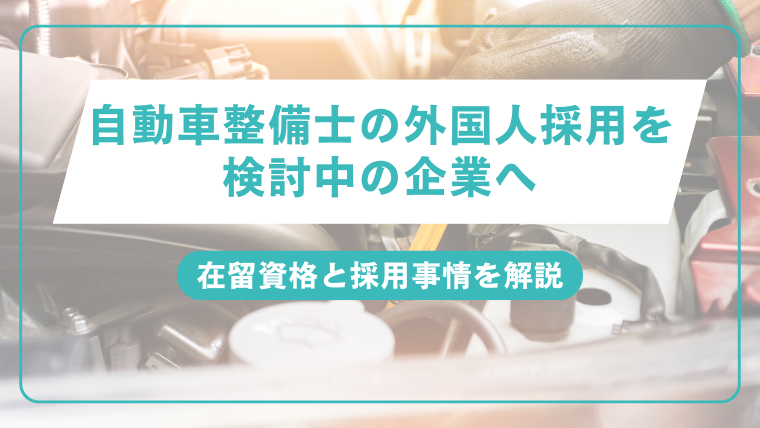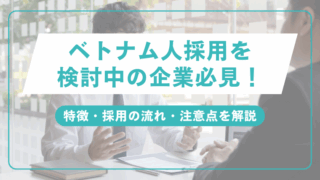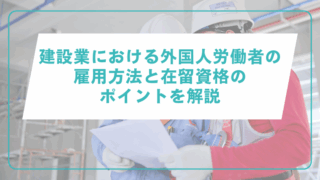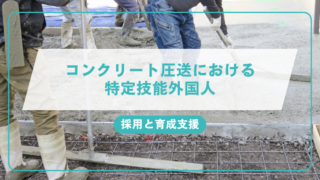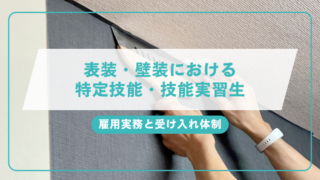自動車整備業界では人材不足の深刻化により、外国人整備士の採用に注目が集まっています。国際的な人材の受け入れが進む中で、在留資格や業務内容の制限など、採用時に理解すべき制度や実務的なポイントも多く存在します。
本記事では、外国人整備士を採用する際の在留資格の種類、業務範囲、採用フロー、注意点やメリットについて、企業が押さえるべき知識をわかりやすく整理しました。初めて外国人採用を検討する企業にも役立つ導入ガイドとしてご活用ください。

外国人整備士の採用、どこから始める?
制度や手続きの流れ、最新の採用事情、人材紹介の活用法までわかりやすくご案内いたします。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
外国人整備士の採用が注目される背景と業界の現状

自動車整備業界における人手不足の実態
日本の自動車整備業界では、慢性的な人手不足が長年の課題となっています。特に中小規模の整備工場では、若年層の採用難・高齢化・離職率の高さが重なり、必要な人材を確保できない状況が続いています。
整備士資格保有者数は年々減少傾向にあり、都市部だけでなく地方でも影響は深刻です。こうした背景のなか、安定して働ける外国人材への注目が高まっており、実務経験や技術力を持つ外国人整備士の採用が一つの選択肢として広がりを見せています。
外国人採用によってもたらされる現場の変化
外国人整備士を採用することで、単なる労働力補填にとどまらず、現場の活性化や組織の多様性の推進といった副次的なメリットも期待できます。具体的には以下のような変化が見られます。
- 多国籍なチーム構成による新たな価値観の共有
- 日本人スタッフの教育意識やマネジメント力の向上
- 海外との取引や外国人顧客対応への柔軟性向上
こうした背景から、「即戦力人材」としての外国人整備士の採用は、今や現場運営における戦略的判断の一つとして定着しつつあります。
外国人自動車整備士に必要な在留資格と業務範囲
自動車整備士として就労可能な在留資格の種類
外国人が日本で自動車整備の業務に従事するためには、適切な在留資格の取得が必須です。特に、以下の2つの在留資格が中心となります。
- 特定技能1号(自動車整備分野)
試験に合格することで就労が可能。即戦力としての業務従事が認められる。 - 技術・人文知識・国際業務
大学などで自動車関連の知識を学び、ホワイトカラー的な業務が中心のポジションに採用されます。現場作業は限定的。
このほか、永住者や日本人配偶者等の在留資格がある場合は、別途許可なく就労できます。ただし、資格外活動許可での就労は原則として認められておらず、注意が必要です。
業務範囲と在留資格の適合関係
在留資格ごとに、従事できる業務内容には明確な違いがあります。
- 特定技能1号:整備、検査、点検、部品交換など、幅広く実作業が可能。
- 技術・人文知識・国際業務:整備マニュアルの翻訳、技術指導、品質管理など、管理・設計的業務に限定。
在留資格と実際の業務に齟齬があると、不法就労と見なされる可能性があるため、配属先の職務設計は慎重に行う必要があります。
資格取得までの流れと試験制度
特定技能1号で就労するためには、「自動車整備分野特定技能評価試験」および「日本語能力評価試験(N4以上)」の合格が必要です。これにより、一定レベルの技術・知識と日本語理解力を持つことが担保されます。
現在、この試験は海外・国内の両方で実施されており、ベトナムやインドネシア、フィリピンなどを中心に多くの候補者が準備を進めています。
採用前に確認すべき要件と手続き
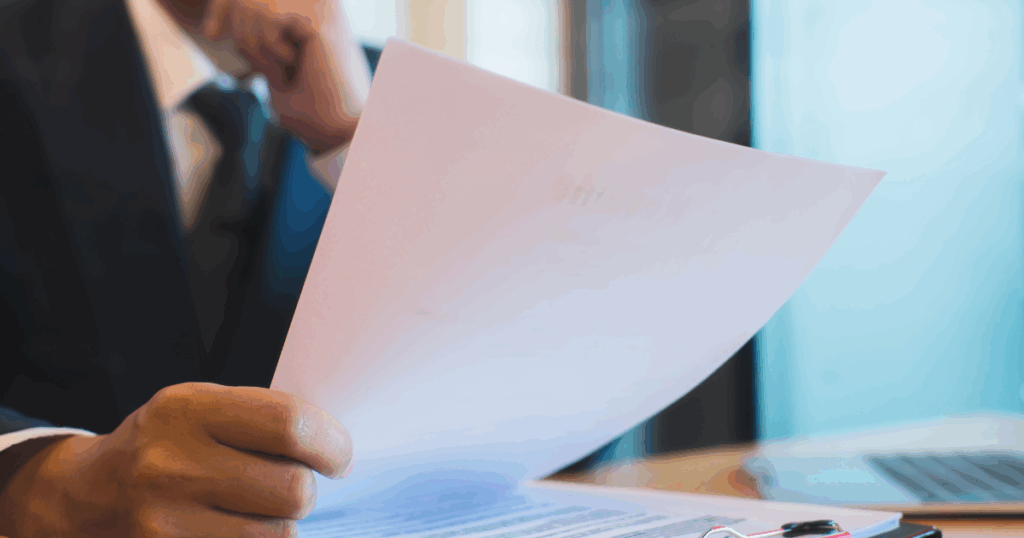
採用時に確認すべき基本情報と書類
外国人の自動車整備士を採用する際、在留資格と関連書類の確認は必須です。
確認すべき主な項目
- 在留カード(表裏両面):在留資格・在留期間・就労制限の有無を確認
- 在留資格認定証明書(内定者の場合)
- パスポートの本人確認ページ
- 日本語能力証明書(N4以上が目安)
- 特定技能評価試験の合格証
在留カードの裏面には、「資格外活動許可欄」や「更新・変更履歴」が記載されているため、必ず確認しましょう。
企業は、本人がどの資格で働けるかを明確に理解し、不適切な配属を行わないことが重要です。
外国人採用時の在留カードについて「外国人採用時の在留カードチェック完全ガイド!確認方法と偽造対策を徹底解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
受け入れ前に必要な申請・手続きの流れ
在留資格の申請や変更は、出入国在留管理庁での手続きが中心になります。主なステップは以下のとおりです。
- 必要書類の準備
- 雇用契約書
- 会社概要資料
- 業務内容説明書など
- 在留資格変更許可申請または認定証明書交付申請
- 申請結果の通知(約1〜2か月)
- 在留カードの取得後、正式入社
また、入社が決定した際は、ハローワークへの雇用保険手続きや外国人雇用状況届出も必要です。社内の人事・労務チームと連携し、スムーズな受け入れ準備を進めましょう。
採用要件のすり合わせと面接時の確認ポイント
書類審査だけでは不十分な場合、面接を通じた実務経験や技術スキルの確認も重要です。以下のポイントを意識しましょう。
- 日本語でのコミュニケーションレベル(作業指示を理解できるか)
- 過去の実務経験(特定の車種・作業内容)
- 長期的な就労意欲と日本文化への適応力
企業が求める技術レベルと、候補者のスキルがマッチしているかの見極めが、採用の成否を大きく左右します。
外国人採用時の面接については「外国人採用の面接質問完全ガイド!注意点からNG質問まで徹底解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。

外国人整備士の採用、どこから始める?
制度や手続きの流れ、最新の採用事情、人材紹介の活用法までわかりやすくご案内いたします。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。
外国人自動車整備士を採用するメリットと職場への影響
多様な人材の導入による組織の活性化
外国人の自動車整備士を採用することは、単なる人手確保にとどまらず、企業の職場環境や組織文化にも良い影響を与えることがあります。
たとえば、以下のような効果が期待できます。
- 業務の標準化:日本語や文化の違いを考慮してマニュアル整備や工程の見直しが進むことで、社内のオペレーションが整います。
- 社員の意識改革:外国人と働くことで、既存社員のグローバルな視点や柔軟な対応力が育ちます。
- モチベーションの向上:前向きに学ぶ外国人整備士の姿勢が、チーム全体に良い影響を与えることもあります。
このように、組織に多様性が加わることで、社内の雰囲気や成長スピードが変わる可能性があります。
スキル・経験に優れた人材の活用
近年では、海外で自動車整備の高度な訓練や教育を受けた人材が増加しており、日本での就労を希望する外国人エンジニアのレベルも上がっています。
- 海外の専門学校・大学で自動車整備を学んだ人材
- 現地ディーラーや整備工場で実務経験を持つ人材
- 特定技能評価試験に合格済みの候補者
これらの人材を採用することで、即戦力として現場で活躍できるケースも多く、育成コストの削減にもつながる可能性があります。
また、自動車整備の知識だけでなく、ITスキルや英語などの語学力を併せ持つ人材もおり、将来的なグローバル展開を視野に入れている企業にとっても大きな戦力になります。
外国人採用によるイメージ向上と企業ブランディング
外国人整備士の受け入れを積極的に行う企業は、ダイバーシティ推進やSDGsに貢献する企業としてのイメージ向上が期待できます。
- 求職者や取引先への信頼感の向上
- 採用広報における差別化
- CSR(企業の社会的責任)への対応強化
多様な人材を受け入れる体制を整えていることが、企業の「働きやすさ」「開かれた環境」を象徴するアピール材料となり、他社との差別化にもつながります。
外国人自動車整備士の採用で注意すべき実務上のポイント

在留資格と業務内容の適合性を必ず確認する
外国人を自動車整備士として雇用する際、最も重要なのが在留資格と実際の業務内容が一致しているかの確認です。たとえば、「特定技能1号」や「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格によって、許可される職務内容や条件が異なります。
- 「特定技能1号」は、あらかじめ整備分野での技能評価試験合格が必要
- 「技術・人文知識・国際業務」は、学歴や実務経験に基づく要件が求められます
- 在留カードの記載内容を確認し、就労制限の有無や有効期間をチェックすることが不可欠です
もしも業務内容が在留資格に適合していない場合、不法就労と見なされるリスクがあるため、採用前に十分な確認と理解が必要です。
雇用契約と労働条件の明示を徹底する
外国人整備士を雇用する場合、日本人と同様に労働基準法に基づいた契約書の作成と労働条件の明示が必要です。言語の違いによって誤解が生じやすいため、以下のような配慮が求められます。
- 母国語や英語での雇用契約書の準備
- 勤務時間、休日、給与体系、社会保険などの条件を具体的に書面で伝える
- 可能であれば、面談時に通訳を同席させ、相互理解を深める
こうした取り組みによって、トラブルを未然に防ぎ、円滑な雇用関係の構築が可能となります。
社内の受け入れ体制を整えておく
外国人整備士の採用には、現場での教育・指導体制の整備や、日本人社員とのコミュニケーションの橋渡しが重要です。
- 作業マニュアルの図解化・翻訳対応
- 教育担当者の指名とOJT体制の整備
- ハラスメント防止や文化理解を含めた社内研修の実施
とくに初めて外国人を受け入れる企業では、文化や価値観の違いに戸惑う場面も出てくるため、事前に対応フローを明確にしておくことが大切です。
また、生活面のサポート(住居手配、行政手続きなど)も含めて支援できる環境を用意することで、定着率の向上にもつながります。
外国人自動車整備士の採用は、人材不足への対応にとどまらず、技術力の向上や職場の多様性促進にも大きく貢献します。特定技能や技術・人文知識・国際業務といった在留資格ごとの要件や業務範囲を正しく理解することで、適切な人材の採用とスムーズな受け入れが可能となります。採用後は、日本語教育や生活支援、社内制度の整備といった定着支援策を継続的に講じることが重要です。企業として、法令遵守と文化理解をもとに、外国人材が活躍しやすい職場づくりを進めることで、長期的な組織の安定と成長が期待できます。

外国人整備士の採用、どこから始める?
制度や手続きの流れ、最新の採用事情、人材紹介の活用法までわかりやすくご案内いたします。
まずは無料相談から、お気軽にお問い合わせください。