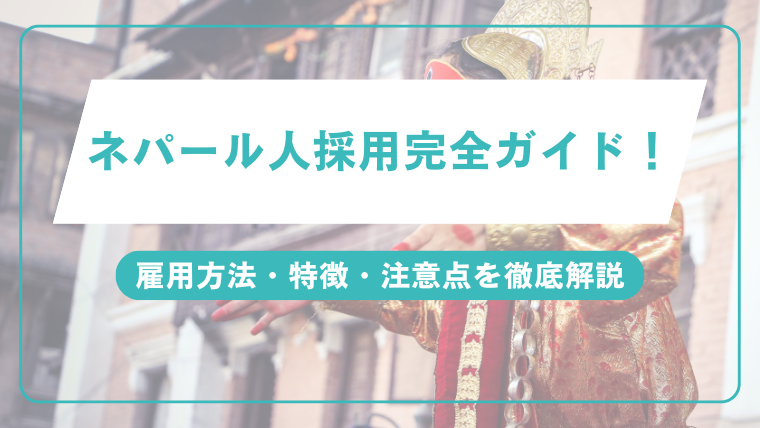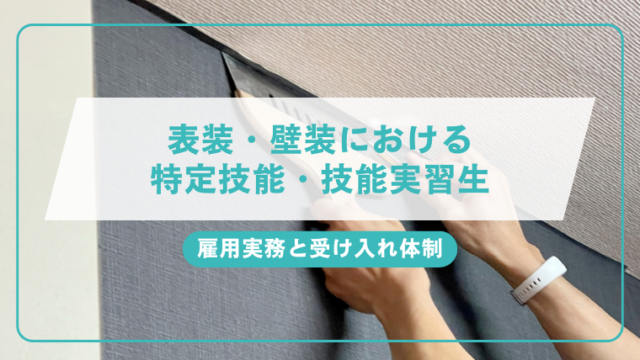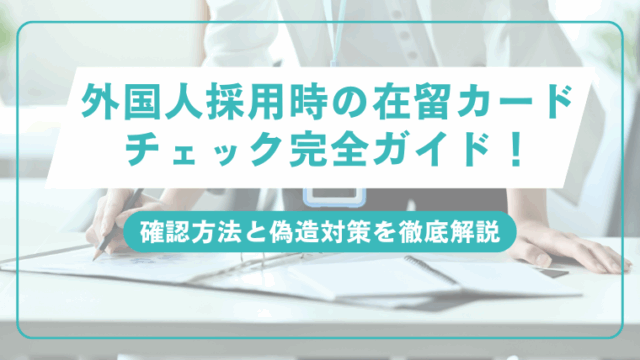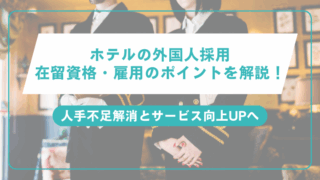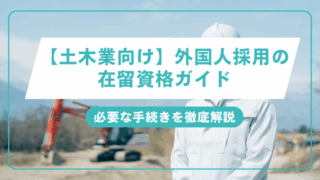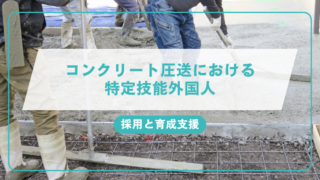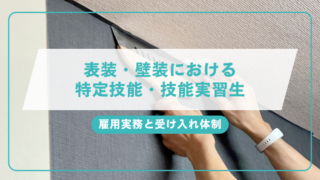近年、真面目で勤勉と評価されるネパール人材への注目が高まり、多くの企業が採用を検討しています。特に製造・介護・建設分野では、日本語能力や適応力の高さを活かし、現場の即戦力として期待されています。しかし、宗教や文化の違い、在留資格の取得・管理には慎重な対応が求められます。本記事では、ネパール人を雇用するうえで知っておくべき特徴や在留資格の種類、採用の流れや注意点、費用相場までを詳しく解説。企業が安心してネパール人採用を進めるために必要な情報を網羅しています。

ネパール人採用が注目される背景とは

労働力不足の深刻化と新興国人材への期待
日本国内の少子高齢化により、特に建設・介護・製造業界を中心に慢性的な人材不足が続いています。こうした中で、若くて意欲的な外国人材への注目が集まっており、特にネパール人「日本語学習意欲が高い」「宗教的に制限が少ない」「真面目で協調性がある」といった点で、採用先の企業から高評価を得ています。
またネパールは多くの国民が海外で働く「出稼ぎ文化」を背景に持ち、日本での就労にも強い関心を持っています。このような背景から、他国と比較しても比較的安定して人材を確保できる点が企業にとって魅力となっています。
ネパール人の国民性と職場での評価
ネパール人は温厚で忍耐強く、集団の中でも調和を大切にする国民性があります。日本企業との相性も良く、接客やチーム作業において高く評価される傾向があります。宗教的にはヒンドゥー教徒と仏教徒が多く、基本的に飲酒・喫煙や食事制限も比較的柔軟なため、日本の生活習慣に溶け込みやすい点もポイントです。
加えて、日本語能力試験(JLPT)N3~N4レベルを取得しているネパール人も多く、教育熱心な傾向があるため、一定の研修を通じて現場で活躍できる可能性が高いといえるでしょう。
ネパール人を雇用する際に必要な在留資格と制度の違い
就労可能な主な在留資格の種類と特徴
ネパール人を日本で雇用する際には、まず「どの在留資格で働くか」を明確にする必要があります。以下のような在留資格が、企業での就労に適用されます。
- 技術・人文知識・国際業務:大学卒業者など、事務・技術・通訳などの業務に従事できる。
- 特定技能1号:介護・建設・宿泊など、人手不足分野に対応。技能試験と日本語能力試験に合格する必要があります。
- 留学からの就職:大学・専門学校を卒業したネパール人が、資格変更を経て就労可能となるケース。
- 永住者・定住者・日本人の配偶者等:資格制限が少なく、幅広い職種での就労が可能。
とくに特定技能は、在留資格としてネパール人の活用が広がっている制度であり、登録支援機関による支援計画が義務づけられる点が特徴です。
在留資格ごとの申請・管理の注意点
在留資格の申請・管理には以下のような注意が必要です。
- 在留資格ごとに「従事できる業務内容」が明確に定められているため、職種のミスマッチがあると不法就労に該当する可能性があります。
- 雇用開始前には「在留カード」の確認を必ず行い、在留期間・資格外活動許可の有無などもチェックします。
- 特定技能の採用では、登録支援機関との契約や定期的な報告義務が発生し、企業側にも一定の体制整備が求められます。
これらの制度的ポイントを理解し、適切に対応することが、ネパール人材の安定雇用と長期定着につながります。
外国人採用の進め方は「外国人採用の進め方と注意点|募集方法・在留資格・支援体制を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
ネパール人雇用のメリットと期待できる効果
勤勉さ・適応力の高さが職場の安定化に寄与
ネパール人労働者の多くは20~30代の若年層で、エネルギーと向上心にあふれています。高齢化が進む日本において、長期的な戦力としての人材確保において非常に有効です。真面目で勤勉な人柄が評価されることが多く、職場における離職率の低さにもつながる傾向があります。上下関係を重んじ、組織ルールに従う姿勢を持つ人が多いため、日本企業の社風にも馴染みやすいとされています。
また、仏教やヒンドゥー教の文化的背景を持ちながらも、多様な宗教や価値観を尊重する傾向があり、異文化環境への適応力にも優れています。こうした点から、チーム内の協調性や現場の安定運営に貢献できる人材として注目されています。
日本語習得意欲が高く、現場でのコミュニケーションにも強み
ネパール人は、日本語の学習意欲が高く、N4〜N2レベルの日本語能力試験(JLPT)に合格している人材も多数います。日々の業務の中でも継続的に言語を吸収しようとする姿勢が見られ、現場での意思疎通に関する評価も上々です。
とくに、介護・飲食・建設など現場での対話が重要視される職種において、日本語での対応力は業務効率や利用者満足度の向上にも直結します。日本語学校や就労前研修を通じて語学支援を行えば、さらに定着率やパフォーマンスの向上が期待できます。
雇用によるグローバル化と職場の活性化
ネパール人をはじめとする外国人材の雇用は、単なる労働力確保にとどまらず、社内のグローバル化やダイバーシティ推進にも寄与します。異文化理解の促進によって、既存の従業員の視野も広がり、チーム全体の活性化につながるケースも少なくありません。
また、ネパール人労働者は地域社会との関係構築にも積極的で、地域イベントやボランティアへの参加などを通じて、地域コミュニティの一員としての役割を果たすこともあります。企業ブランディングや地域貢献の面でもプラスの効果が期待されます。
ネパール人を採用する際の在留資格と就労分野の整理
主な在留資格の種類と採用対象となる職種
ネパール人を日本で雇用する際には、該当する在留資格を確認することが最も重要なステップです。以下に、採用時に検討されやすい主な在留資格と、その対象となる職種を整理します。
技術・人文知識・国際業務
大学卒業程度の学歴があり、事務職・通訳・ITエンジニア・貿易業務などのホワイトカラー職が対象。在留資格要件を満たせば、ネパールの大学卒業者も対象となります。
留学
留学生がアルバイトする場合は「資格外活動許可」が必要で、週28時間以内の就労制限があります。卒業後、在留資格変更により就職も可能です。
就労可能な分野と採用判断のポイント
在留資格によっては、就労できる業務内容が厳密に定められており、職種と資格の不一致によるトラブルも発生しやすいため、採用前に以下のようなポイントを確認することが重要です。
- 在留カードの「就労制限の有無」欄を必ずチェック
- 予定している業務内容が資格に適合しているか、事前に行政書士などに確認
- 「永住者」や「定住者」「日本人の配偶者等」の場合は、職種の制限なく雇用可能
在留資格の制限を誤解したまま雇用を開始すると、不法就労とみなされ企業側も罰則対象となるリスクがあるため、慎重な確認が求められます。
在留資格の取得・変更・更新に関する注意点
採用後に在留資格を新たに取得する、または変更・更新する必要があるケースも少なくありません。その際には以下の点に注意しましょう。
- 申請には本人のパスポート・在留カード、雇用契約書、会社案内、業務内容の説明書などの提出が必要
- 「技術・人文知識・国際業務」などは学歴や業務内容の証明が必要で、審査に時間がかかることもある
- 更新時には直近の給与支払い実績や労働時間実績が審査されるため、日頃の就労管理が重要
企業としても申請書類の準備や入管とのやり取りをサポートし、申請がスムーズに進むよう協力体制を整えることが求められます。
ネパール人採用の注意点と雇用環境整備のポイント

宗教・文化への配慮と職場コミュニケーション
ネパール人を雇用する際は、宗教的・文化的背景に対する理解と配慮が重要です。特に以下のようなポイントに注意が必要です。
- 食文化の違い:ネパールにはヒンドゥー教・仏教徒が多く、牛肉を口にしない、ベジタリアンであるなどの食習慣が見られます。職場の給食や懇親会では事前に確認し、選択肢を設けると安心です。
- 宗教行事の尊重:ダサインやティハールなどの伝統的な祝祭があり、帰国休暇や宗教上の希望に対する柔軟な対応が求められます。
- 言語や指示の伝え方:日本語に不慣れな場合もあるため、指示を出す際は平易な日本語を使い、確認や繰り返しによって誤解を防ぐことが有効です。翻訳アプリや社内通訳のサポートも検討しましょう。
契約内容・就労条件の明確化とトラブル予防
文化や言語の違いにより、労働条件の誤解が生まれやすいのもネパール人採用の特性です。以下のような取り組みが、雇用トラブルの予防に効果的です。
- 雇用契約書はやさしい日本語、もしくは母国語併記にする
- 労働時間、休日、残業代の支給条件などは、図表や事例を用いて丁寧に説明する
- 入社時のオリエンテーションで、労働基準法の基本や会社ルールをしっかり伝える
特に「言った・言わない」の行き違いは後の離職や不信感につながりやすいため、説明内容は記録として残し、定期的な確認も行うとよいでしょう。
外国人採用時の雇用契約書について「外国人採用の雇用契約書ガイド|作成時の重要ポイント、注意点を徹底解説!」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
生活支援・定着支援の取り組み
安定的な就労を実現するには、生活支援の体制づくりも重要です。ネパール人は来日時に日本での生活環境に不安を感じることが多く、定着率にも影響します。
- 住居の確保:初期住居の紹介や契約支援、通勤手段の確保もサポートすると安心感につながります。
- 生活相談の窓口:ゴミ出しルール、公共交通の使い方、銀行口座の開設など、日本の生活様式に関する情報提供が必要です。
- 日本語学習の機会:業務外でも日本語学習を継続できるよう、オンライン教材の紹介や社内勉強会の開催が効果的です。
- メンタル面のフォロー:異国で働く中で不安や孤独感を抱くケースもあるため、定期面談や同国籍の先輩社員による相談窓口の設置も有効です。
このような支援が「働きやすさ」につながり、結果として職場の定着率向上にも寄与します。
外国人採用における定着と離職防止は「外国人材の定着と離職防止のポイントを解説|企業が行うべき人事施策について」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
ネパール人の採用は、単なる人手不足の解消にとどまらず、若年層人材の確保、職場の活性化、多様性の促進など、企業に多くのメリットをもたらします。文化的・宗教的な違いを理解し、丁寧な支援体制を構築することで、現場への定着率は大きく向上します。特に、在留資格の適切な確認や生活支援、日本語研修などの準備を怠らなければ、ネパール人材は職場の信頼できる戦力となるでしょう。今後の国際人材戦略を見据えたとき、ネパール人の採用は企業にとって大きな可能性を秘めています。