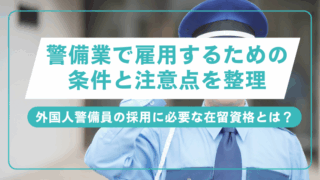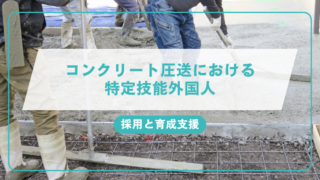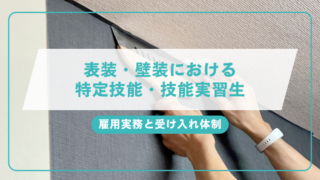「リフォーム現場に人が足りない」そんな悩みを抱える企業にとって、外国人材の活用は現実的な選択肢です。
この記事では、外国人リフォーム職人を採用する際に必要となる在留資格の種類や手続き、制度選択の注意点を実務目線で整理。技能実習・特定技能・身分系在留資格の違いもわかりやすく解説し、合法的かつ安定的な受け入れのヒントをお届けします。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
リフォーム業で外国人を雇用する背景と現状

人手不足が深刻化する現場作業の実態
高齢化と若年層の建設業離れにより、内装・外装・設備系リフォーム職種における人材確保は年々難しくなっています。とくに地方や中小規模の工事現場では、職人の高齢化率が50%を超えるエリアもあり、現場の維持すら困難な状況も見られます。
こうしたなか、外国人労働者が現場作業の担い手として注目されています。施工や補修といった技能を持つ外国人材は、教育次第で即戦力にもなり得るため、業界全体で受け入れニーズが拡大しています。
外国人労働者数の推移と建設業の位置づけ
厚生労働省の統計によれば、建設分野で働く外国人労働者数は2023年時点でおよそ5万人。その多くが技能実習や特定技能で就労しており、増加傾向にあります。リフォーム業は建設業の一種として扱われ、在留資格の取り扱いにも建設業と共通点が多くなっています。
リフォーム業と相性のよい外国人材の特徴
外国人労働者のなかには、細かい作業や清掃・片付け、工具管理など、ルールのある作業を正確にこなす特性を持つ人材が少なくありません。また、日本語能力試験N3以上を取得している人材であれば、現場での意思疎通も比較的スムーズです。
真面目で勤勉な人材をしっかりと受け入れ・育成できれば、長期的な人材確保にもつながります。
リフォーム業での外国人採用に必要な在留資格の種類
リフォーム業で適用される主な在留資格
リフォーム業で外国人を合法的に雇用するためには、業務内容に応じた適切な在留資格を取得してもらう必要があります。対象となる主な在留資格は次の3つです。
| 在留資格の種類 | 対象業務と特徴 | 雇用可能な業務内容 |
| 特定技能(1号) | 建設業全般の熟練労働者向け。技能評価試験と日本語試験が必要。 | 解体、内装仕上げ、建築板金、塗装など、リフォーム業に関連する222職種の範囲内で従事可 |
| 技能実習 | 技能移転が目的。監理団体を通じた受け入れ。 | 内装・建築大工・配管等、職種限定かつ実習計画に基づいた業務 |
| 身分に基づく在留資格(永住者・日本人の配偶者等) | 制限なしに就労可能。個人事情により滞在。 | 制限なくあらゆる業務が可能。清掃や補助作業も含む |
制度ごとの違いと注意点
技能実習と特定技能は混同されがちですが、制度目的が異なります。
・技能実習:日本の技術を習得・帰国後に活かす目的
・特定技能:即戦力として日本国内での労働力確保が目的
身分系在留資格を持つ外国人は、法的な制限がほぼないため、求人の自由度が高い反面、雇用管理や条件交渉を日本人と同様に行う必要があります。
・特定技能の外国人を採用する際には、登録支援機関と連携して支援体制を構築することが義務化されており、受け入れ側の負担も一定数あります。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
採用手続きの流れと必要な書類
外国人を採用するまでの基本ステップ
外国人をリフォーム現場に雇用するには、在留資格の種類に応じて異なる手続きが必要です。以下は、特定技能を例とした代表的な流れです。
- 業務内容と在留資格のマッチングを確認
→ 該当する在留資格(特定技能/技能実習/身分系)を決定 - 事前の要件確認と準備
→ 特定技能の場合、技能評価試験と日本語試験の合格が必要
→ 受け入れ体制(支援計画・日本語サポートなど)の整備 - 書類作成と申請手続き
→ 在留資格認定証明書交付申請、雇用契約書などを提出
→ 入国管理局による審査 - 在留カードの取得・就労開始
→ 入国後、在留カードが交付され、指定の業務に従事可能に
外国人採用の進め方は「外国人採用の進め方と注意点|募集方法・在留資格・支援体制を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
必要書類の一覧とポイント
| 書類名 | 概要 | 特記事項 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 雇用予定の外国人が日本に入国・在留するための基礎資料 | 雇用主が代理申請する場合が多い |
| 雇用契約書 | 業務内容・給与・労働条件などを明記 | 日本語と母国語の両言語で準備が望ましい |
| 技能評価試験・日本語試験の合格証明書 | 特定技能1号の要件 | 職種ごとに異なるため事前確認が必要 |
| 登録支援機関との契約書(特定技能のみ) | 支援体制を外部委託する場合に必要 | 自社で支援体制を構築する場合は不要 |
・書類不備や曖昧な記載は審査に大きな影響を与えるため、内容は慎重に確認することが重要です。
・技能実習制度を利用する場合は、監理団体を通して申請・調整が行われるため、自社での直接申請はできません。
・提出タイミングにも注意が必要で、申請から認定までに1〜3か月を要するケースもあります。
特定技能と技能実習の違いを正しく理解する
制度の目的と背景の違い
「技能実習」と「特定技能」は、制度の目的そのものが異なります。
| 制度名 | 制度の目的 | 雇用の位置付け | 滞在可能期間 |
| 技能実習 | 技能の移転を通じた国際貢献 | 労働力ではなく人材育成 | 原則最長5年 |
| 特定技能 | 日本国内の人手不足への対処 | 即戦力の労働力として受け入れ | 最大5年(1号)/無期限(2号) |
技能実習は“育成”が目的であり、現場での戦力として扱うことは原則的にNGです。一方、特定技能は明確に「労働力としての受け入れ」が目的であり、現場に即した人材配置が可能です。
対象業務と要件の違い
リフォーム業界が関係するのは、建設分野の中でも内装仕上げ/とび/防水などの一部職種に限られます。そのうえで、以下のような違いがあります。
| 項目 | 技能実習 | 特定技能 |
| 対象職種 | 国際的に技術移転が可能と認められた職種(例:とび・内装仕上げなど) | 厚労省・国交省等が人手不足と認定した建設分野 |
| 要件 | 監理団体への加入・実習計画の認定 | 技能試験/日本語試験の合格、建設キャリアアップシステム登録など |
| 雇用形態 | 実習生としての受け入れ | 雇用契約による直接雇用 |
現場目線で見る制度選択のポイント
・即戦力を求めるなら特定技能が適している
→ 技能・日本語試験を突破しており、現場での基本的な指示理解が期待できる
・長期的な育成を視野に入れる場合は技能実習も選択肢に
→ 制度上、段階的なスキルアップと定期的な移行が必要
なお、技能実習から特定技能1号への移行も可能であり、技能実習満了者が日本で引き続き働く道として活用されています。
採用後に注意すべき管理・教育のポイント
法令遵守と就業条件の明確化
外国人労働者の雇用では、労働基準法や出入国管理法などの法令を確実に遵守することが前提です。以下のような点は、企業側の管理責任として明確にしておく必要があります。
・労働時間、休日、有給休暇の規定を日本人と同等に設定
・社会保険(厚生年金・健康保険)の適用と手続き
・雇用契約書は日本語と母語の2言語で交付(トラブル防止)
在留カードの確認や、有効期限切れの管理徹底も重要です。資格外活動や不法残留を避けるためには、定期的な確認と更新手続きのサポートが求められます。
職場定着に必要な教育と支援
特定技能1号で受け入れる場合は、企業または登録支援機関による義務的支援10項目の提供が求められます。
たとえば、
・日本での生活オリエンテーションの実施
・生活に関する相談・苦情対応(日本語で対応困難な場合は多言語サポート)
・日本語学習機会の提供(eラーニングや対面講座など)
職場定着率を高めるためには、業務面の教育だけでなく、生活支援も含めたトータルサポートが不可欠です。
外国人採用における定着と離職防止は「外国人材の定着と離職防止のポイントを解説|企業が行うべき人事施策について」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
外国人に伝わりやすい指導の工夫
・図や写真を多用したマニュアルの整備
・ゆっくり・簡潔な日本語での指示
・技能試験の内容に沿ったOJTを実施(特定技能2号を見据える場合)
外国人労働者の不安や孤立を減らすためにも、「わからないことは聞いていい」という安心感を与える環境づくりが大切です。
リフォーム業での受け入れに必要な在留資格の取得フロー
採用から在留資格取得までの基本ステップ
リフォーム業界で外国人を採用する際は、職種や国籍、在留資格の種類に応じて申請フローが異なります。以下は、特定技能1号の場合の代表的な流れです。
| ステップ | 内容 | 備考 |
| 採用計画の策定 | 対象職種・業務内容を明確に | 特定技能の対象業務か確認 |
| 試験・日本語能力確認 | 技能評価試験・日本語能力試験(N4以上) | 国によっては海外での受験も可 |
| 雇用契約の締結 | 労働条件を明示し契約 | 2言語での交付推奨 |
| 支援計画の策定 | 登録支援機関と連携または自社で提供 | 義務的支援10項目が必要 |
| 在留資格申請 | 入管庁へ必要書類を提出 | 審査期間は1〜2ヶ月程度 |
| 入国または在留資格変更 | 新規入国または資格変更 | 出入国在留管理庁で確認 |
| 配属・支援開始 | 就業スタート+支援体制稼働 | 初期オリエンテーション実施 |
技能実習からの移行や身分系在留資格の場合は、この限りではありません。とくに「永住者」「日本人の配偶者等」などは制約が少なく、個別に在留資格変更申請を行うのみで受け入れが可能です。
申請時に必要となる書類と注意点
在留資格の申請には、以下のような複数の証明書や書類の整備が必要です。
・雇用契約書
・労働条件通知書
・支援計画書(または登録支援機関との契約書)
・技能試験・日本語試験の合格証明書
・企業の登記事項証明書、決算報告書 など
また、企業側に「人材確保の必要性」や「外国人を受け入れる体制の整備」が認められないと、審査が通らない可能性もあります。採用前から準備を進め、行政書士などの専門家と連携することが安全策になります。
まとめ

リフォーム業界において外国人労働者を採用するには、業務内容に適した在留資格の選定と、法令に基づく受け入れ準備が欠かせません。とくに「特定技能」は即戦力となる人材の確保に有効ですが、制度理解と支援体制の整備が必要です。
また、「技能実習」や「身分系在留資格」などは要件や支援義務の有無が異なるため、自社の業務や管理体制に合った制度を選ぶことが重要です。適切な申請手続きを行うことで、現場に即した人材の安定確保が可能となります。
採用を検討する企業は、在留資格ごとの特徴を正しく把握し、早期からの情報収集と準備を行うことが成功への第一歩となります。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/