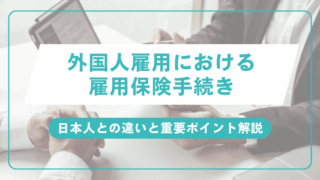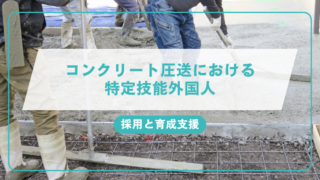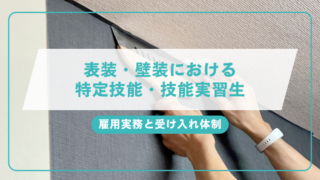日本では少子高齢化と労働人口の減少により、多くの業界で人手不足が深刻化しています。
この問題に対応するため、外国人労働者の採用が注目され、建設・製造・介護・外食業などを中心に積極的な受け入れが進められています。
しかし、外国人雇用は日本人採用と異なり、在留資格の管理や法的規制、文化の違いなどに留意する必要があります。
採用手続きや労働条件を正しく理解しなければ、トラブルや法的リスクにつながる可能性があります。
本記事では、外国人採用のメリットや課題、手続きの流れ、費用、注意点などを包括的に解説します。
これから外国人材の活用を検討している企業担当者の方に向けて、実務で役立つ情報をわかりやすく整理していますので、ぜひ参考にしてください。
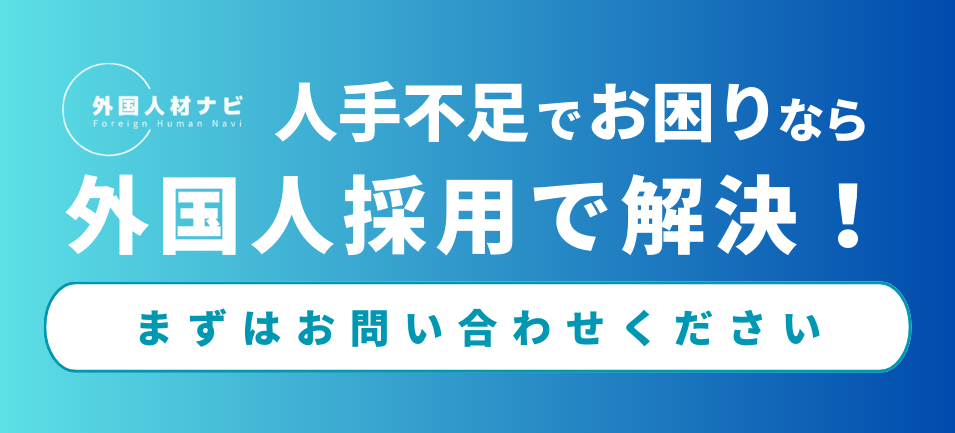 外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人採用の現状と採用のメリット・課題
日本の労働市場では、外国人労働者の受け入れが急速に拡大しています。特に、人手不足が深刻な業界では、安定した労働力を確保するために、外国人材の活用が不可欠な状況となっています。
政府もこの流れを受け、特定技能制度の導入や在留資格の拡充を進めており、企業にとっては外国人採用がより身近な選択肢となっています。しかし、外国人雇用にはメリットだけでなく、言語や文化の違い、在留資格管理の負担などの課題もあります。
ここでは、外国人労働者の増加の背景と人手不足問題、企業にとってのメリットと課題を詳しく解説します。
外国人労働者が増加する背景と日本の人手不足問題
1. 労働人口の減少と人手不足の深刻化
日本では少子高齢化が進み、生産年齢人口(15~64歳)が減少しています。これにより、特に以下の業界では深刻な人手不足が発生しています。
- 介護業界:高齢化が進む一方で、介護職の担い手が不足
- 建設業界:インフラ整備や災害復旧の需要が増加
- 製造業:生産現場の担い手が減少し、技術継承が課題
- 外食・宿泊業:訪日外国人の増加に伴い、サービス業の人材確保が急務
このような状況を受け、外国人労働者の活用が避けられない現実となっています。
2. 政府による外国人材受け入れ拡大の動き
人手不足対策として、政府は外国人労働者の受け入れを拡大する政策を推進しています。主な制度には以下のようなものがあります。
- 技能実習制度:開発途上国の人材が日本の技術を学ぶことを目的とした制度
- 特定技能制度:特定の業界で即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格
- 技術・人文知識・国際業務ビザ:専門的な知識・スキルを持つ外国人の雇用を可能にする制度
これらの制度により、外国人が日本で働く環境が整いつつあり、企業にとっても採用しやすい状況が生まれています。
3. 外国人労働者の増加と今後の展望
現在、日本に在留する外国人の数は約320万人(2023年時点)を超えており、そのうち就労目的の外国人も増加しています。特に、特定技能や技能実習制度を利用した外国人労働者の数は今後さらに増える見込みです。
企業が外国人採用を検討する際は、これらの背景を理解し、適切な人材確保の戦略を立てることが重要になります。
外国人採用による企業のメリットとは?
外国人採用は、人手不足の解消だけでなく、企業の成長や競争力向上にもつながる重要な施策です。特に、国際市場への展開や職場の多様性を重視する企業にとって、外国人労働者の活用は有効な選択肢となります。
1. 労働力不足の解消
2. グローバル化への対応
3. 職場の活性化と生産性向上
4. 助成金や支援制度の活用
外国人を採用する際の課題と解決策
1. 言語・コミュニケーションの壁
外国人採用における日本語力向上の社内教育などについては「外国人採用における日本語レベルと教育支援|業務定着に必要な確認ポイントと対策を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
2. 文化・価値観の違い
3. 在留資格の管理と法的リスク
4. 生活環境の整備と定着率の向上
外国人を採用する前に押さえておくべき基本事項
① どのような外国人が雇用できるのか?在留資格による違い
外国人を採用する際、在留資格によって就労の可否や可能な業務範囲が決まっている。在留資格を適切に確認し、業務に合った資格を持つ人材を採用することが重要。
- 技術・人文知識・国際業務:専門的な業務(エンジニア、通訳、デザイナーなど)
- 特定技能:人手不足が深刻な特定16分野(介護、建設、外食業など)
- 技能実習:技能を習得することを目的とし、一定期間就労が可能
- 企業内転勤:海外の関連企業から日本へ転勤する従業員
- 留学・家族滞在:原則就労不可だが、資格外活動許可を取得すればアルバイトが可能
- 観光ビザ(短期滞在):一切の就労不可
採用時には、在留カードを確認し、在留資格が業務内容に適合しているかを慎重にチェックする必要があります。
② 日本人と同等の待遇が求められる雇用ルールとは?
外国人を雇用する際、日本人と同等以上の待遇を提供することが法律で義務付けられている。これは、不当な低賃金労働や労働環境の悪化を防ぐための措置であり、適切な雇用管理が求められます。
- 最低賃金の適用:外国人労働者にも最低賃金法が適用されるため、各都道府県の最低賃金を下回る給与設定は不可
- 労働時間・残業管理:労働基準法に基づき、勤務時間・休憩・休日を適正に管理する必要がある
- 社会保険の加入義務:健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの適用対象となるため、加入手続きを適切に行う
- 日本人と比較して不利な待遇をすることは禁止されており、昇給や福利厚生の面でも公平な扱いが求められる
- 特に技能実習生や特定技能外国人の給与が、同業務の日本人より低く設定されることは違法となる可能性がある
適切な待遇を提供することで、外国人労働者の定着率を向上させ、長期的な雇用につなげることができます。
③ 企業が守るべき外国人雇用の法律とリスク管理
外国人を雇用する際、企業は関連する法律を遵守し、不法就労や労働環境の問題を未然に防ぐ必要がある。適切なリスク管理を行わなければ、企業側も処罰の対象となるため、法令の正しい理解が求められます。
- 入管法(出入国管理及び難民認定法):在留資格に適した業務で雇用する義務がある。資格外活動を行わせると「不法就労助長罪」に該当し、企業も罰則の対象となる。
- 労働基準法:労働時間や賃金に関する規定は外国人にも適用され、日本人と同等の労働条件を提供しなければならない。
- 雇用対策法:外国人雇用を行う場合、企業はハローワークに対して雇用状況を届け出る義務がある。未届け出は罰則の対象となる。
- 労働安全衛生法:危険作業を伴う業務では、適切な安全管理と教育を実施し、労働災害を防ぐ必要がある。
- 在留資格の確認・管理を徹底する:雇用前に在留カードを確認し、雇用後も在留期限の管理を怠らない。
- 適切な労働条件を確保する:低賃金や長時間労働を強いることなく、日本人と同等の待遇を提供する。
- コンプライアンス研修の実施:外国人雇用のルールや文化的配慮について、社内での理解を深める研修を実施する。
- 行政書士や専門機関との連携:法改正やビザ申請手続きの変更など、最新情報を把握し、適切に対応できる体制を構築する。
法律を正しく理解し、適切な管理体制を整えることで、外国人雇用のリスクを最小限に抑え、安定した雇用環境を構築することが可能となります。
外国人採用の手順と必要な手続き
-visual-selection.png)
① 求人募集の方法と外国人採用のルート(国内・海外)
外国人採用を成功させるためには、適切な採用ルートを選択し、ターゲットに合った求人方法を活用することが重要です。国内と海外の採用ルートには、それぞれ特徴がありますので、自社のニーズに合わせた手法を選びましょう。
- 求人サイト・ハローワーク:外国人向けの求人サイトやハローワークを活用し、求職者にアプローチする方法です。
- 大学・専門学校からの紹介:留学生を対象に、大学や専門学校と連携して採用を行います。日本で学んだ外国人材は、日本の文化や言語に適応しやすい点がメリットです。
- 外国人向けの人材紹介会社:登録済みの求職者と企業をマッチングするサービスを利用することで、迅速な採用が可能になります。
- 海外の人材紹介会社・現地リクルート:海外に拠点を持つ人材紹介会社を活用し、直接採用する方法です。特定技能や技能実習制度を活用する企業によく利用されています。
- 技能実習生の受け入れ:技能実習制度を利用し、海外から人材を受け入れる方法です。一定期間の就労後に特定技能へ移行するケースも増えています。
- SNSや求人広告:FacebookやLinkedInなどのSNSを活用し、海外の求職者に直接アプローチする手法もあります。特に、ITエンジニアや専門職の採用に適しています。
採用ルートを選ぶ際には、在留資格の取得や必要な手続きの違いも考慮する必要があります。国内採用は比較的スムーズですが、海外採用はビザ申請や入国手続きが必要になるため、スケジュールをしっかりと管理しましょう。
② 在留資格の有効性を確認する(在留カードのチェック)
外国人を採用する際には、必ず在留資格の有効性を確認し、適切な資格であることを確認することが重要です。在留資格によって就労の可否や可能な業務範囲が異なるため、雇用契約を結ぶ前に適合性をしっかりとチェックしましょう。
- 在留カードの両面コピーを取得し、定期的に確認する
- 入管庁のオンラインシステムを活用し、在留資格の確認を行う
- 在留期限が近づいたら、従業員に更新手続きを促し、必要に応じてサポートする
不法就労を防ぐためにも、在留カードの確認は企業の責任として徹底することが求められます。万が一、不適切な在留資格で雇用してしまった場合、企業側も法的責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。
③ 採用面接で確認すべきスキルや日本語能力の基準
外国人を採用する際、業務に適したスキルや日本語能力を持っているかを確認することが重要です。職種や業務内容に応じて、適切な基準を設けることで、雇用後のミスマッチを防ぐことができます。
- 簡単な日本語で業務に関する質問を行い、意思疎通のレベルを測る
- 過去の職務経験や対応した業務について具体的に話してもらう
- 必要に応じて筆記試験や実技試験を実施し、実務能力を評価する
企業側が明確な基準を持ち、適切な面接を実施することで、採用後のスムーズな業務遂行につなげることができます。
関連記事:外国人採用の面接質問完全ガイド!注意点からNG質問まで徹底解説
④ 労働契約の締結と雇用手続き(契約内容と注意点)
外国人を雇用する際は、労働契約の内容を明確にし、適切な手続きを行うことが重要です。契約内容の不備や誤解を防ぐために、日本の労働法に基づいた適正な雇用条件を提示し、外国人従業員が理解できる形で説明する必要があります。
- 契約書は日本語と母国語の両方で作成し、内容を十分に理解してもらう
- 労働条件通知書を必ず交付し、書面で合意を得る
- 試用期間の有無や更新条件を明確にする
労働契約の締結を適切に行うことで、外国人従業員との信頼関係を築き、安定した雇用につなげることができます。
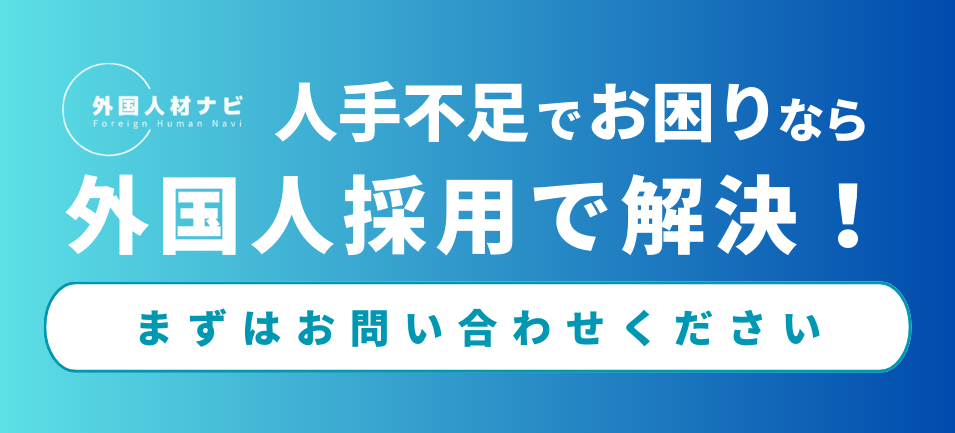 外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
⑤ 在留資格の取得・変更の流れ(必要書類と申請のポイント)
外国人を雇用する際には、適切な在留資格を取得・変更する必要があります。企業は、申請手続きや必要書類を理解し、スムーズな手続きをサポートすることが求められます。
- 必要な在留資格の確認:業務内容に適した在留資格を選定し、取得または変更の必要性を確認する。
- 必要書類の準備:雇用契約書、会社概要、在留資格申請書などを揃え、出入国在留管理庁へ提出する。
- 申請手続きの実施:外国人本人または企業の代理人(行政書士など)が申請を行い、審査結果を待つ。
- 許可取得後の手続き:新しい在留カードを受け取り、労働条件や社会保険の適用を確認する。
- 在留資格変更許可申請書または在留資格認定証明書交付申請書
- 雇用契約書(労働条件が明記されたもの)
- 会社概要(登記簿謄本、決算書など)
- 外国人本人の履歴書や学歴証明書
- 在留カードのコピー
- 業務内容と在留資格の適合性を事前に確認する
- 書類に不備がないよう、行政書士などの専門家に相談することも検討する
- 審査には1~3か月かかることがあるため、計画的に進める
適切な手続きを行い、在留資格の管理を徹底することで、外国人従業員が安心して働ける環境を整えることができます。
⑥ 入社準備と企業がサポートすべき生活環境の整備
外国人従業員がスムーズに業務を開始し、日本で安定した生活を送るためには、企業側の適切なサポートが欠かせません。特に、住居の確保や生活インフラの整備を支援することで、早期離職のリスクを軽減できます。
- 業務研修の実施:仕事内容や社内ルール、ビジネスマナーを説明し、職場環境に早く適応できるよう支援する。
- 日本語サポートの提供:業務に必要な日本語を学べる機会を設け、円滑なコミュニケーションを促す。
- 通勤経路の確認:最寄り駅やバス停などの交通手段を案内し、スムーズな通勤をサポートする。
- 住居の手配:外国人が入居可能な賃貸住宅を紹介し、契約の手続きを支援する。保証人が必要な場合、企業がサポートするケースもある。
- 行政手続きの支援:住民登録や銀行口座の開設、健康保険の加入手続きをサポートし、日本での生活基盤を整える。
- 生活必需品の準備:家電や生活用品の購入をサポートし、必要に応じて地域の生活情報を提供する。
- 定期的な面談の実施:仕事や生活面での悩みをヒアリングし、早期離職を防ぐ。
- 文化交流の促進:社内イベントや交流会を開催し、職場のチームワークを向上させる。
企業が入社前後のサポートを充実させることで、外国人従業員の職場定着を促し、長期的な雇用につなげることができます。
外国人採用にかかる費用と期間について知る
採用コストの内訳(求人・ビザ手続き・教育コストなど)
外国人を採用する際には、日本人採用とは異なる費用が発生します。採用コストを事前に把握し、適切な予算を確保することが重要です。
- 求人・採用活動費:求人広告の掲載費、採用エージェントの手数料(成功報酬型が一般的)
- ビザ申請関連費:在留資格認定証明書交付申請費用(4,000円)、行政書士への依頼費用(約5万~15万円)
- 渡航費:海外から採用する場合、航空券代や入国時の手続き費用
- 研修・教育費:日本語研修、業務研修、異文化適応研修の実施費用
- 生活サポート費:住居手配費用、保証人代行サービス、生活用品の準備費用
採用コストは、採用ルートや国籍によって大きく異なります。国内採用は比較的コストが抑えられますが、海外からの直接採用では、ビザ取得や渡航費などの負担が増える点に注意が必要です。
採用コストを抑える方法など、より詳しい外国人採用の費用については「外国人採用にかかる費用とコストを徹底解説!コストを抑える対策も紹介」にて解説しています。
外国人採用の期間はどれくらい?国内採用と海外採用の違い
外国人採用にかかる期間は、国内在住者を採用する場合と、海外から新たに呼び寄せる場合とで大きく異なります。採用スケジュールを事前に把握し、余裕を持った計画を立てることが重要です。
- 求人募集・面接(2~4週間)
- 在留資格の確認・雇用契約の締結(1~2週間)
- 入社準備(2~4週間)
国内在住の外国人はすでに在留資格を持っているため、ビザ申請の手続きが不要なケースが多く、比較的スムーズに採用できます。
- 求人募集・面接(1~2か月)
- 在留資格認定証明書の申請・取得(2~3か月)
- 渡航準備・入国手続き(1か月)
海外からの採用では、在留資格の取得や渡航手続きに時間がかかるため、長期的な計画が必要です。特に、特定技能や技能実習制度を活用する場合は、各国の送り出し機関との調整も含めて、6か月以上かかることもあります。
人材紹介会社の利用から内定・契約まで(国内外共通)
外国人採用をスムーズに進めるためには、人材紹介会社(エージェント)を活用する方法が有効です。特に、海外採用の場合は、現地の送り出し機関や採用支援会社との連携が不可欠となります。
- 人材紹介会社との契約
- 求める職種やスキル、在留資格に適した人材を紹介してもらうため、契約を締結する。
- 手数料は成功報酬型が一般的で、年間給与の20~30%程度が相場。
- 候補者の選定と書類審査
- エージェントが紹介した候補者の履歴書や資格を確認し、面接を実施する。
- 特定技能や技能実習の場合は、対象分野の技能試験や日本語能力のチェックが必要。
- 面接・適性試験の実施
- 企業担当者がオンラインまたは対面で面接を行い、スキルや日本語能力、勤務意欲を確認する。
- 職種によっては、実技試験や筆記試験を実施するケースもある。
- 内定・雇用契約の締結
- 採用が決定したら、雇用契約書を作成し、労働条件を明確にする。
- 日本語と母国語で契約書を用意し、雇用条件について十分に説明することが重要。
人材紹介会社を活用することで、適切な人材を効率的に確保でき、採用業務の負担を軽減できるため、特に海外採用を検討している企業には有効な手段となります。
文化や価値観の違いを理解し、職場の多様性を推進する
外国人従業員を受け入れる際には、文化や価値観の違いを理解し、多様性を尊重する職場環境を整えることが重要です。文化的なギャップが原因で誤解やトラブルが発生しないよう、企業側が積極的に対策を講じる必要があります。
- 仕事に対する考え方の違い
- 日本では「報連相(報告・連絡・相談)」が重視されるが、国によっては自主性を尊重する働き方が一般的。
- 時間感覚の違い
- 「定時厳守」を重視する日本とは異なり、時間に対する考え方が柔軟な国もある。
- 宗教や生活習慣の違い
- イスラム教徒の礼拝時間や食事制限など、配慮が必要なケースがある。
- 外国人向けの業務マニュアルを用意し、日本の職場文化やルールを明確に伝える
- 社内で異文化理解の研修を実施し、日本人社員の意識を向上させる
- 休憩時間や社内ルールを柔軟に運用し、多様な価値観を受け入れやすい環境を整える
文化の違いを理解し、互いに尊重し合うことで、働きやすい職場づくりと組織の活性化につながります。
まとめ:外国人採用を成功させるために
外国人採用を成功させるには、適切な在留資格の確認、労働条件の整備、文化や価値観の違いへの配慮が欠かせません。さらに、採用後のサポートを充実させることで、職場への定着率を高め、長期的な雇用につなげることができます。
企業が外国人採用のメリットと課題を理解し、適切な対応を行うことで、人材不足の解消だけでなく、組織の活性化やグローバルな成長にもつながります。今後の労働市場の変化を見据え、外国人材を積極的に活用することが求められます。
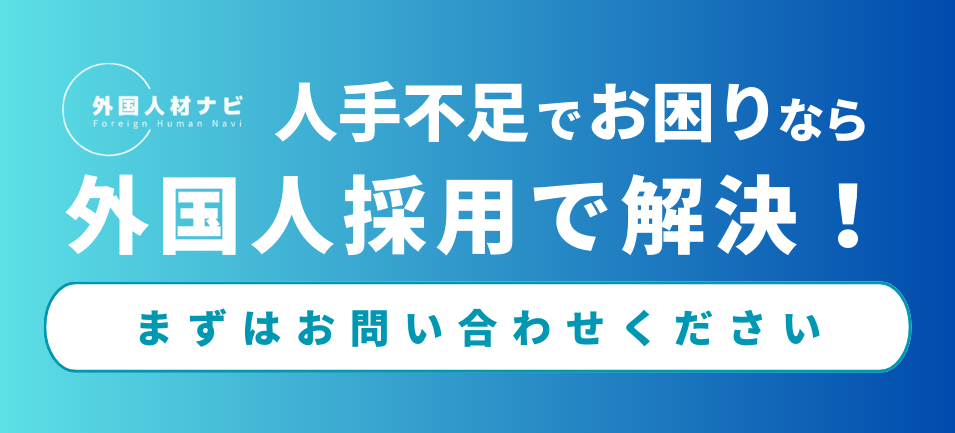 外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!人手不足にお悩みの企業・店舗様はまずはお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/



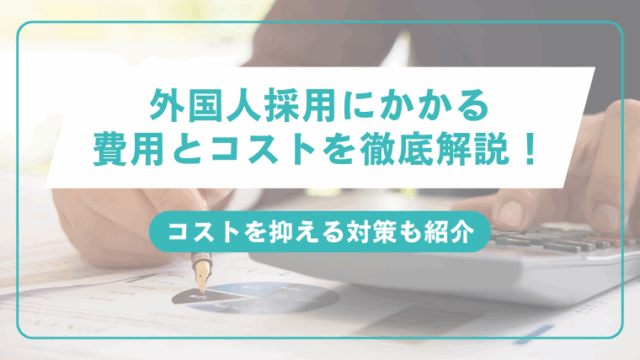
-640x360.png)