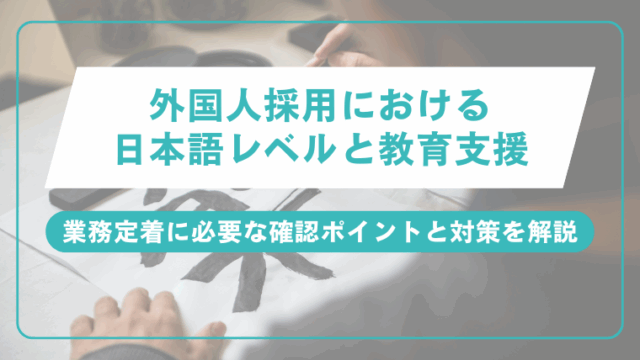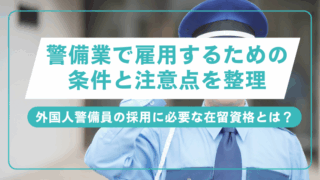技能実習制度は、日本の企業が発展途上国の外国人に技術を習得してもらうことを目的とした制度です。しかし、実習生を受け入れるにはさまざまな費用が発生し、事前にしっかりとコストを把握しておく必要があります。
特に、送り出し機関や監理団体への支払い、渡航費、研修費、給与、社会保険料など、企業が負担する費用は多岐にわたります。本記事では、技能実習生の受け入れにかかる費用の内訳を詳しく解説し、コストを抑えるためのポイントや支援機関の活用方法についても紹介します。
外国人技能実習生の受け入れにかかる費用とは?
外国人技能実習生を受け入れる際には、企業が負担する費用と、技能実習生本人が負担する費用がそれぞれ発生します。受け入れにかかる費用を正しく理解し、適切に管理することが重要です。
受け入れにかかる費用の主な種類
| 費用の種類 | 主な項目 | 負担者 |
| 受け入れ前の初期費用 | 送り出し機関・監理団体への支払い、渡航費、入国手続き費用、講習費 | 企業・技能実習生本人 |
| 受け入れ後の継続費用 | 給与、社会保険料、労働関連費用、住居・生活費補助 | 企業 |
特定技能との費用比較
技能実習生と特定技能外国人では、企業が負担する費用の内容が異なります。
【技能実習生】
- 監理団体を通じた受け入れが基本のため、監理費用が発生する。
- 研修費や講習費が必須であり、特定技能よりも受け入れ初期費用が高い傾向がある。
【特定技能外国人】
- 監理団体は不要だが、登録支援機関を利用する場合はその委託費がかかる。
- 技能実習生よりも給与が高くなることが一般的で、長期雇用のコストが増加する。
技能実習生の受け入れでは、監理団体の活用や助成金の利用など、適切なコスト管理が必要になります。
受け入れ前にかかる初期費用
技能実習生を受け入れる前には、さまざまな初期費用が発生します。特に、送り出し機関や監理団体への支払い、渡航費、入国手続き、研修費用などが大きな割合を占めます。
送り出し機関・監理団体への支払い
技能実習生を受け入れるには、送り出し機関と監理団体の2つの機関が関与します。
送り出し機関とは?
技能実習生の母国で、日本への派遣手続きを行う機関です。主な業務には、以下のようなものがあります。
- 技能実習生の募集・選考
- 日本語教育・マナー研修の実施
- 渡航手続きの支援
監理団体とは?
監理団体(協同組合など)は、日本国内で企業と技能実習生のサポートを行う機関です。主な業務には、以下のようなものがあります。
- 技能実習生の定期的な訪問・指導
- 実習計画の作成・管理
- 企業と実習生のトラブル対応
発生する費用の目安
| 費用項目 | 費用目安 | 負担者 |
| 送り出し機関への手数料 | 30万円~50万円/人 | 企業 |
| 監理団体への管理費 | 月額3万円~5万円/人 | 企業 |
送り出し機関と監理団体を利用することで、スムーズな受け入れが可能になりますが、費用がかかる点に注意が必要です。
渡航費・入国手続き費用
技能実習生が日本で働くためには、渡航費や在留資格の申請費用などの手続きにかかる費用を負担する必要があります。これらの費用は、企業側と技能実習生本人が分担するケースが一般的です。
発生する費用の目安
| 費用項目 | 費用目安 | 負担者 |
| 渡航費(航空券代) | 5万円~15万円/人 | 技能実習生本人(企業が負担する場合もあり) |
| 在留資格申請手数料 | 4,000円~6,000円/人 | 企業または技能実習生本人 |
| 入国時の健康診断費用 | 1万円~3万円/人 | 企業 |
費用が発生する背景
- 渡航費は実習生本人が負担するケースが多いですが、企業が負担することで優秀な人材を確保しやすくなります。
- 在留資格の取得には手数料が必要で、申請を行政書士に委託する場合は、追加で5万~10万円の費用が発生することもあります。
- 入国時の健康診断は、労働安全管理の一環として実施が推奨されており、企業が負担するのが一般的です。
コストを抑えるポイント
- 渡航費を企業が一部補助し、技能実習生の経済的負担を軽減することで、離職リスクを抑えられる。
- 申請手続きを自社で行い、行政書士の手数料を削減する。
- 健康診断の団体割引を活用し、コストを抑える。
講習・研修費用
技能実習生は入国後、一定期間の講習や研修を受けることが義務付けられています。この講習期間中は、実際の業務には従事せず、生活指導や日本語教育、安全講習などを受ける必要があります。
発生する費用の目安
| 費用項目 | 費用目安 | 負担者 |
| 入国後講習(1カ月間) | 約15万円~30万円/人 | 企業 |
| 日本語研修費用 | 3万円~5万円/人 | 企業 |
| 労働安全講習 | 1万円~3万円/人 | 企業 |
講習の主な内容
- 日本の生活ルールやマナーの指導
- 日本語教育
(業務で必要な会話や読み書き) - 労働安全に関する研修
(業界ごとの安全対策)
費用が発生する背景
- 技能実習制度では、入国後に最低1カ月の講習が義務付けられているため、企業が負担する必要がある。
- 日本語研修を実施することで、職場でのコミュニケーションミスを防ぎ、業務効率を向上させる。
- 労働安全講習は、事故防止の観点から重要視されており、特に建設業や製造業では必須となる。
コストを抑えるポイント
- 監理団体が提供する研修プログラムを活用し、コストを最適化する。
- 日本語研修はオンライン学習を活用し、費用を削減する。
- 複数名の技能実習生をまとめて研修し、1人あたりの費用を軽減する。
受け入れ後に継続してかかる費用
技能実習生を受け入れた後も、企業には継続的な費用負担が発生します。特に、給与・社会保険料・住居費・生活サポート費用などがあり、長期的なコスト管理が求められます。
給与・社会保険料・労働関連費用
技能実習生は、日本人労働者と同様に最低賃金の適用を受け、社会保険にも加入する必要があります。
発生する費用の目安
| 費用項目 | 費用目安 | 負担者 |
| 給与(基本給) | 月額16万円~(地域により変動あり) | 企業 |
| 残業代(割増賃金) | 時給換算で25%増 | 企業 |
| 健康保険・厚生年金・雇用保険 | 給与の約15%~20% | 企業・技能実習生本人 |
| 労災保険 | 業種によるが企業が全額負担 | 企業 |
費用が発生する背景
- 技能実習生の給与は、都道府県の最低賃金以上である必要がある。
- 残業をさせる場合、労働基準法に従い、適正な割増賃金を支払う必要がある。
- 社会保険は、日本人労働者と同様に加入義務があり、企業が一定割合を負担する。
コストを抑えるポイント
- 労働時間を適正に管理し、不必要な残業を減らす。
- 社会保険料の軽減措置(助成金活用など)を検討する。
- 複数年の雇用を前提とした計画的な受け入れを行い、採用コストを分散する。
生活サポート費用(住居・食事・交通費)
技能実習生を受け入れる際、住居の提供や生活費の支援が必要になることが一般的です。企業がどの範囲まで負担するかによって、実習生の生活環境や定着率にも影響を与えます。
発生する費用の目安
| 費用項目 | 費用目安 | 負担者 |
| 住居費(家賃) | 月額3万円~7万円/人 | 企業または技能実習生本人 |
| 水道光熱費 | 月額5,000円~1万円/人 | 技能実習生本人(企業負担の場合もあり) |
| 食事手当 | 月額5,000円~1万円/人 | 企業(任意) |
| 交通費(通勤) | 月額5,000円~1万円 | 企業または技能実習生本人 |
費用が発生する背景
- 住居の確保は企業の義務であり、社宅やアパートを契約するケースが多い。
- 技能実習生の給与から家賃を天引きすることも可能だが、企業が一部補助することで定着率を向上させることができる。
- 交通費の負担は企業ごとに異なるが、公共交通機関を利用する場合は支給するケースが多い。
コストを抑えるポイント
- 社宅・寮を活用し、住居費の負担を軽減する。
- 複数名の技能実習生を同じ住居に住まわせ、家賃コストを分散する。
- 食事手当の支給を工夫し、実習生の生活負担を軽減しながら雇用満足度を向上させる。
技能実習生の受け入れコストを抑えるポイント
技能実習生の受け入れにはさまざまな費用が発生しますが、工夫次第で企業の負担を軽減することが可能です。以下に、コスト削減のための具体的な方法を紹介します。
助成金・補助金の活用
外国人労働者の受け入れに対して、政府や自治体が助成金や補助金を提供しています。
- 職業訓練・日本語教育補助金
技能実習生向けの研修費用を補助。 - 人材確保等支援助成金
雇用環境の整備や教育研修の実施を支援。
住居や研修費用の負担軽減策
- 社宅・寮を活用する
複数名の実習生を同じ住居に住まわせ、家賃負担を抑える。 - 日本語教育をオンライン学習に切り替える
コストを削減しつつ、学習機会を提供。 - 社宅・寮を活用する
複数名の実習生を同じ住居に住まわせ、家賃負担を抑える。 - 日本語教育をオンライン学習に切り替える
コストを削減しつつ、学習機会を提供。
監理団体の適切な選定
監理団体によって管理費用が異なるため、複数の団体を比較し、費用とサポート内容のバランスを考慮して選定することが重要です。
支援機関の活用|オープンケア協同組合の紹介
技能実習生の受け入れには、監理団体の選定や手続きの管理、生活サポートなど、多くの業務が発生します。こうした負担を軽減するために、適切な支援機関を活用することが重要です。その中でも、「オープンケア協同組合」は、企業の負担軽減とスムーズな受け入れを支援する機関として注目されています。
監理団体の役割とは?
監理団体(協同組合など)は、企業と技能実習生の間に入り、受け入れや実習期間中の管理・支援を行う機関です。主な業務には以下の内容が含まれます。
- 技能実習生の受け入れ手続きのサポート
- 入国後講習の実施(日本語教育・生活指導)
- 企業と技能実習生の定期的な面談・指導
- 労働環境や生活環境のチェック
オープンケア協同組合を活用するメリット
技能実習生の受け入れをスムーズに進めるためには、適切な監理団体の選定が重要です。その中でも、オープンケア協同組合はコストの最適化と充実したサポート体制を強みとし、多くの企業に選ばれています。
1. 低コストでの受け入れが可能
オープンケア協同組合は、1000社以上の組合員が参加する大規模なネットワークを活用し、運営コストを削減しています。これにより、質の高い管理・サポートを低コストで提供することが可能です。
2. インドネシア人材に特化した確保保証
- インドネシア人技能実習生の採用に強みを持ち、安定した人材確保が可能。
- 経験豊富な監理支援スタッフが在籍しており、専門的なノウハウを企業に提供。
3. 充実した受け入れ支援
- 技能実習生の住居手配、生活用品の準備、通信環境の整備まで幅広くサポート。
- 商談時に、実際に日本語を学ぶ技能実習生とコミュニケーションを取る機会を提供し、高い日本語能力を実感できる。
オープンケア協同組合を活用することで、コストを抑えつつ、実習生のスムーズな受け入れと定着を実現できます。企業の負担を最小限に抑えながら、安定した外国人材の確保を目指す企業にとって、最適なパートナーとなるでしょう。
まとめ:技能実習生の受け入れ費用を適正化し、持続可能な雇用を実現しよう
技能実習生の受け入れには、送り出し機関や監理団体への支払い、渡航費、講習費、給与、住居費など、さまざまなコストが発生します。特に、受け入れ前の初期費用と、継続的な生活・労働関連費用を正しく理解し、計画的に管理することが重要です。
企業の負担を軽減するためには、助成金の活用、社宅や寮の提供、監理団体の適切な選定が有効です。また、「オープンケア協同組合」などの支援機関を活用することで、受け入れの手続きや実習生の管理をスムーズに進めることができ、長期的に安定した雇用の実現につながります。
技能実習生の受け入れを成功させるためには、コストだけでなく、適切なサポート体制を整え、実習生が安心して働ける環境を作ることが不可欠です。計画的な受け入れを行い、企業と技能実習生双方にとって最適な雇用環境を構築していきましょう。
企業様の人手不足を解消する有効な手段として、外国人労働者を採用される企業様が増えています。本記事をご覧いただいた企業様についても、人手不足の解消に向けて外国人労働者採用を検討されてみてはいかがでしょうか。
外国人採用の基礎の解説については外国人採用の基礎!雇用のメリットや注意点、費用などを丸ごと解説をご参照ください。