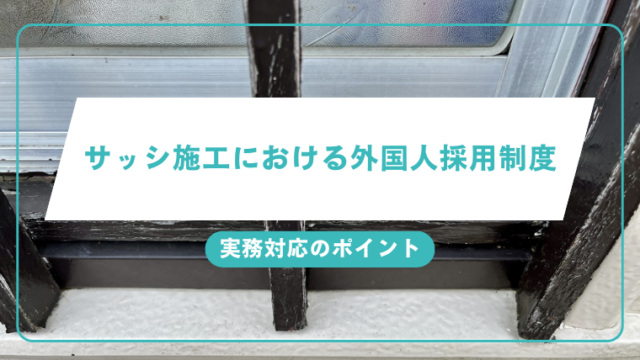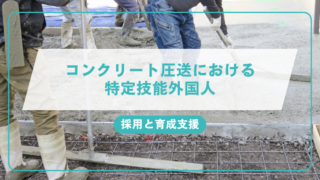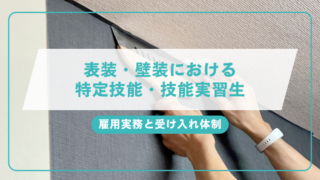外国人労働者を雇用する企業は、雇用の開始や終了時に「外国人雇用状況届出書」の提出が法律で義務付けられています。しかし、提出対象や期限、記載すべき内容など、実務担当者が迷いやすいポイントも多く、対応を誤ると罰則のリスクも生じます。本記事では、届出制度の概要から提出書類・タイミング・注意点までを整理し、正確かつ効率的な届出対応をサポートします。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人雇用状況届出書とは何か?制度の概要と目的
外国人労働者を雇用する企業には、外国人雇用状況届出書の提出が法律で義務付けられています。これは単なる書類作成にとどまらず、適正な雇用管理と行政への正確な情報提供のために重要な役割を担っています。制度の基本を押さえ、正確な届出ができる体制づくりが求められます。
雇用対策法に基づく企業の義務
雇用対策法第28条により、外国人労働者を雇用・離職させた企業は届出の義務があります。国籍を問わず、雇用保険の適用有無に関係なく対象となり
- 雇用保険被保険者資格取得届は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出
- 離職時は、被保険者が離職した日の翌日から10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出
採用日または離職日から10日以内の届出が必要です。ただし、特別永住者・外交官・公用ビザ保有者などは対象外とされています。この制度は、外国人労働者の適正な雇用を推進するために設けられています。
外国人労働者の雇用管理と行政の関係
この制度は、企業と行政の間で外国人雇用の透明性と安全性を確保するための橋渡しの役割を担っています。ハローワークなどの行政機関は、届出情報を基に以下の管理を行います。
- 外国人の就労状況の把握と適正な在留資格管理
- 不法就労の防止
- 雇用政策・施策のデータベース構築
企業側にとっても、適正な届出を行うことで、コンプライアンスの強化や不法就労リスクの回避に役立ちます。行政との連携により、よりスムーズな採用活動と外国人労働者の保護が可能になります。
届出の対象となるケースと提出すべきタイミング
外国人雇用状況届出が必要となるのは、以下のようなケースです。
- 新規雇用時:雇入れ日から10日以内に提出
- 離職時:退職日から10日以内に提出
- 在留資格や雇用条件の変更時:内容に応じて再提出が必要になる場合あり
また、短期雇用やアルバイトであっても、在留カードを保有する外国人労働者であれば届出義務の対象です。在留カードに記載された情報との整合性が求められるため、記載ミスや漏れに注意が必要です。
雇用フローの中に届出を確実に組み込む社内ルールを整備することで、義務を確実に果たすことができます。
新規雇用時に提出すべき情報と書類
外国人労働者を新規に雇用した場合、企業は外国人雇用状況届出書をハローワークへ提出する義務があります。在留カード情報や在留資格、雇用保険の適用有無に応じた書類の区分を確認し、正確な届出を行うことが重要です。提出に不備があると、行政指導や罰則の対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
必要な記載項目(在留カード情報、在留資格、雇用形態など)
届出に必要な主な項目は以下の通りです。
- 氏名(ローマ字表記含む)
- 性別・生年月日・国籍
- 在留カード番号・在留資格・在留期間
- 雇用開始日・雇用形態(正社員・パート等)
- 勤務場所・労働時間・賃金
これらの情報は在留カードや雇用契約書をもとに正確に転記する必要があります。
「雇用保険の適用の有無」によって変わる提出区分
雇用保険の適用対象かどうかで、届出様式や提出方法が異なります。
- 雇用保険加入者:被保険者資格取得届と同時に届出可能
- 雇用保険非加入者:別途「外国人雇用状況届出書」の提出が必要
適用の有無に応じて、正しい様式の選択と期限内の提出が求められます。
ケース別の提出情報(特定技能、留学生アルバイト、永住者など)
外国人の在留資格ごとに届出の留意点が異なります。下記に代表的なケースを整理します。
- 特定技能:分野により就労可能な業務が限定されており、在留資格の確認が不可欠です。
- 留学生アルバイト:資格外活動許可の取得が必要。週28時間以内の労働制限にも留意が必要です。
- 永住者・定住者:原則として日本人と同様に取り扱われますが、届出義務はあります。
これらのケースでは、就労内容・資格の範囲・活動制限の有無を事前に確認し、届出内容との整合性を保つことが重要です。
離職時に必要な手続きと注意点
外国人労働者が退職した際にも、企業は外国人雇用状況届出書の提出義務があります。離職日は雇用状況の大きな転換点であり、届出を怠ると法令違反となる可能性があるため、正確で迅速な対応が求められます。
離職から10日以内に届出が必要
外国人労働者が自己都合・会社都合を問わず離職した場合、企業はその事実を10日以内にハローワークへ届け出る必要があります。
- 提出期限:離職日から起算して10日以内
- 提出様式:外国人雇用状況届出書(離職届、様式第3号の2)
この届出は、雇用保険の被保険者かどうかにかかわらず全ての外国人労働者が対象です(ただし、特別永住者など一部の例外あり)。
離職者情報の記載内容とハローワークの提出先
届出書には、以下のような項目を正確かつ最新の情報で記載する必要があります。
- 離職者の氏名・在留資格・在留カード番号
- 雇用終了日(実際の最終出勤日)
- 雇用保険の適用有無(被保険者番号)
- 雇用形態(正社員、契約社員、アルバイト等)
- 雇用契約終了の理由(会社都合・自己都合など)
また、提出先は雇用事業所の所在地を管轄するハローワークです。郵送・窓口提出のほか、「外国人雇用状況届出システム」を利用した電子申請も可能です。
在留資格と雇用形態が一致しているかを正確に記載することが重要です。不備があると入管の確認時に問題となる可能性があり、帰国や転職の手続きにも影響します。
退職理由記載の注意点
退職理由は、企業都合か自己都合かを明確に記載する必要がありますが、外国人労働者の場合は特に文化的・言語的な背景による誤解を防ぐ表現が求められます。
注意すべきポイント
- 「社内の都合により契約満了とした」など、曖昧な表現を避ける。
- 本人の意思での退職である場合、「自己都合退職」と明記する。
- ビザ更新の影響がある場合は、記録とは別に本人に適切な情報提供を行う。
退職理由の記載は、在留資格の更新や転職に影響する重要事項です。
「懲戒」など誤解を招く表現は避け、事実に基づいた記載を本人と確認のうえ行うことが大切です。不安があれば社労士など専門家に相談する体制も整えておきましょう。
在留資格変更・契約更新時の届出要否
外国人労働者の雇用期間中に「在留資格の変更」や「契約の更新」「部署異動」などが発生することは珍しくありません。これらの変化があった場合、外国人雇用状況届出書の提出が必要かどうかを正しく判断することが、法令順守と適切な労務管理につながります。
契約延長・部署異動などのケースでの判断基準
契約内容に変更があった場合でも、届出の要否は変更の種類と範囲によって異なります。特に多いのが、以下のようなケースです。
届出が不要なケース
- 契約期間の更新(契約内容に変更がない場合)
- 部署異動や勤務地変更(労働条件が大きく変わらない場合)
- 同一業務・同一条件での再契約
これらは継続雇用の範囲内とみなされるため、届出は不要とされています。ただし、在留資格の活動内容と業務が一致していることが前提条件です。
届出が必要なケース
- 契約更新に伴い労働条件が大きく変わる場合(就労時間、給与など)
- 職種変更などにより、従事する業務の内容が変わる場合
- 新たな事業所に配属される場合(転籍に近い形)
このような変更は、雇用内容の本質的な変更とみなされ、新たな届出が求められるケースが多くあります。
判断が難しい場合は、ハローワークや厚生労働省のガイドラインを確認したうえで、必要に応じて社労士や専門家に相談することが望ましいです。
在留資格変更が届出に及ぼす影響と対応
外国人労働者が在留資格を変更する場合、たとえば「留学生」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更するといったケースでは、届出の提出が義務となります。
在留資格変更後の対応ポイント
- 変更後10日以内に、外国人雇用状況届出書を提出
- 新たな在留カードの情報(在留資格名・期間・番号)を反映
- 変更後の雇用形態や業務内容との整合性を再確認
留学生が就労ビザに変更し正社員となった場合、新規雇用として届出が必要です。
在留資格変更が不許可となった場合は、就労継続ができず、契約解除などの対応が必要になります。企業は資格の有効期限や適合性を定期的に確認し、管理体制を整えることが重要です。
在留資格は外国人労働者の就労可否を左右する重要な要素です。変更の有無にかかわらず、資格内容と雇用内容の適合性を常に確認する習慣が、法的リスクを避けるためにも重要です
提出先・提出期限・提出方法を正しく把握
外国人雇用状況届出書を提出の際は、「いつ・どこに・どのように」を正しく把握することが重要です。提出期限の遅れや提出先の誤り、記載ミスがあると、行政指導や罰則の対象となる可能性があります。
原則の提出期限
新規雇用・離職の場合:事実発生から「10日以内」
- 例:4月1日付けで採用した場合は、4月10日までに提出。
- 例:4月15日付けで退職した場合は、4月25日までに提出。
例外や補足
- 10日以内が土日祝日にあたる場合:翌営業日までに提出
- 月末一括処理ではなく、事実発生の都度提出が必要
- 複数人まとめて処理する場合も、個々の発生日基準で判断すること
期限管理を怠ると、行政からの指導対象となり、悪質な場合は30万円以下の罰金が科される可能性もあるため、社内でスケジュール管理を徹底しましょう。
提出先・オンライン提出の流れと注意点
外国人雇用状況届出書の提出先は「管轄のハローワーク」です。ただし、近年では利便性向上のために、「外国人雇用状況届出システム」による電子申請も活用されています。
提出方法の選択肢
- 紙で提出する場合
- 最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)へ直接持参または郵送。
- 郵送提出時は、「控え返送用の返信用封筒と切手」を忘れずに同封。
- オンライン提出の場合
- 「外国人雇用状況届出システム」(厚生労働省提供)からログイン。
- 企業ID登録後、対象者の情報を入力し、電子提出が可能。
注意点
- 紙と電子の二重提出は不要
- 電子提出後は受付完了メールを保存すること
- マイナンバーは記載不要
- 在留カードの写し提出は不要(届出書に記載すればOK)
オンライン提出は、多拠点展開している企業や大量雇用時に効率的ですが、初回登録や操作に慣れるまでは、手間がかかることもあります。提出方法は社内の体制や業務フローに応じて選択しましょう。
ハローワーク提出と外国人雇用状況届出システムの違い
紙での提出(ハローワーク)と、電子申請(外国人雇用状況届出システム)には、それぞれ以下のようなメリット・注意点の違いがあります。
| 比較項目 | ハローワーク提出(紙) | 外国人雇用状況届出システム(電子) |
| 提出方法 | 持参・郵送 | オンライン入力・提出 |
| 受付時間 | 平日8:30~17:15 | 24時間対応(メンテナンス除く) |
| 処理の早さ | 混雑時に時間がかかる | 即時提出・確認が可能 |
| 手間 | 手書き記入・郵送などの準備が必要 | 事前の企業ID登録が必要 |
| 記録管理 | 紙の控えで保管 | 電子データとして保存・出力可能 |
どちらの方法にもメリットはありますが、正確かつ効率的な届出を行うには、電子申請が推奨される傾向にあります。特に人材が多い企業では、処理の標準化や管理効率の面で電子化の利点が大きいです。いずれの方法でも提出期限と記載内容の確認を徹底し、社内でのチェック体制を整えることが重要です。
記入ミス・漏れによる罰則と企業リスク
外国人雇用状況届出書の記載ミスや漏れは、罰則や行政指導の対象となる可能性があり、企業の信頼にも関わります。厚生労働省が義務付ける制度である以上、記載内容の正確さと社内の確認体制が不可欠です。
記載内容の具体的な注意点
外国人雇用状況届出書には、以下のような重要項目が記載必須です。いずれも情報精度が求められ、ひとつでも不備があると再提出や指導の対象になります。
特に注意すべき項目
- 氏名(在留カード記載通り、フリガナ含む)
- 在留資格と在留期間の記入(誤記は重大なミス)
- 在留カード番号(読み間違いに注意)
- 雇用開始日/離職日(遅延や日付不一致に注意)
- 就労の可否および資格外活動許可の有無
- 職種・業務内容(在留資格と整合性が取れているか)
- 雇用保険の適用有無
これらの項目は在留資格管理にも直結するため、入力ミスは制度違反につながります。手書きの場合は書式や読みやすさにも注意し、控えの保管も必須です。資格変更や更新時には最新の在留カード情報で再提出が必要となることがあり、情報共有が不十分だと誤提出のリスクが高まります。社内の労務管理体制と連携の徹底が求められます。
提出漏れ・虚偽記載の罰則と企業への影響
外国人雇用状況届出書に関しては、雇用対策法第28条に基づく義務として明確に規定されており、提出漏れや虚偽記載が確認された場合、以下のような罰則が科される可能性があります。
法的罰則と行政処分
- 提出義務違反・虚偽記載等:30万円以下の罰金(雇用対策法第38条)
- 複数回の違反:指導票の発行やハローワークからの是正指導
- 悪質な違反と判断された場合:求人掲載の制限や企業名の公表措置
実務的なリスク
- 人材紹介会社や行政との信頼低下
- 外国人応募者への不利益発生によるトラブル(例:在留資格更新が困難になるなど)
- 監査・調査時に過去の提出状況を確認されることがあるため、社内記録の不備が問題化しやすい
「知らなかった」「忘れていた」では免責されず、届出は企業の法的義務です。人事・労務担当が制度を正確に理解し、ダブルチェックや記録管理の体制を整えることがリスク回避につながります。提出ミスはヒューマンエラーでは済まされず、行政からは怠慢と見なされる可能性があるため、予防策の徹底が不可欠です。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
ケース別に見る提出対応と実務上のポイント
外国人雇用状況届出書の提出においては、雇用形態や在留資格の種類、雇用保険の適用状況などに応じて提出内容や手続きが異なります。一律ではないため、ケースごとに対応を整理しておくことが、ミスや漏れの防止に不可欠です。以下に代表的なケースごとのポイントを解説します。
雇用保険加入の有無で変わる提出内容
外国人労働者が雇用保険の被保険者となるか否かによって、提出すべき届出の内容や書類が変わります。
雇用保険の被保険者となる場合
- 届出書には雇用保険の被保険者番号を記載
- ハローワークの雇用保険資格取得届と併せて提出
- 「氏名」「在留資格」「在留カード番号」「雇用開始日」などの情報が必須
雇用保険の適用外となる場合(週20時間未満の勤務など)
- 被保険者番号の記載は不要
- 雇用開始・終了のみを報告する簡易様式で対応
- 学生アルバイトや短時間労働者に該当するケースが多い
保険適用の判断を誤ると、提出内容に齟齬が生じ、再提出や指導の対象になることもあるため、労働条件の確認と併せて対応を行いましょう。
外国人雇用時の雇用保険については「外国人雇用における雇用保険手続き、日本人との違いと重要ポイント解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
特定技能・技能実習・留学生アルバイトの扱い
在留資格の種類によっても届出の取扱いが異なります。特に以下の在留資格は、企業側にとって届出義務と確認事項が多いため、対応には注意が必要です。
特定技能(1号・2号)
- 対象分野(介護・建設・外食業など)に応じた支援計画の整備が必要
- 登録支援機関を活用している場合でも、企業に届出義務がある
- 雇用保険適用の有無にかかわらず届出が必須
技能実習
- 監理団体を通じた就労となるが、実習実施者(企業)も届出義務を負う
- 実習開始・終了・失踪時など、ハローワークへの即時届出が必要
- 在留資格や就労内容との整合性確認も重要
留学生アルバイト(資格外活動)
- 原則として「週28時間以内」などの制限付きで就労可能
- 雇用保険は原則適用外だが、届出は必要
- 雇用開始時に「資格外活動許可書」の有無を確認し、記録に残す
制度の枠組みに応じた対応を取ることが、在留資格トラブルや指導リスクの回避につながります。
派遣社員・短期雇用者のケース
直接雇用以外の形態、または短期契約の労働者にも原則として届出義務があります。ただし、対応方法や書類の提出タイミングには細かな違いがあるため、以下の点を把握しておきましょう。
派遣社員(人材派遣会社を通じて雇用)
- 届出義務は派遣元事業主(派遣会社)にあります
- 派遣先企業は、派遣元と連携して、在留資格の確認・業務内容の適合性のチェックを行う責任があります
- 不明点があれば、派遣元を通じてハローワークに相談するのが望ましい
短期雇用者(例:1か月未満の契約)
- 雇用期間が短くても、在留カードを確認し、届出が必要
- 特に短期間で複数の外国人労働者を雇う業種(飲食業・製造業など)は、提出漏れが起こりやすいため注意
ケースによって提出の有無や内容が変わるため、社内の担当者が各パターンを事前に把握しておくことが重要です。
なお、実務上は以下のようなフローを整備することが推奨されます(社内マニュアルの一例)
- 採用決定後、在留カードを確認
- 雇用契約書の内容と在留資格の適合性をチェック
- 雇用保険適用の有無を判断
- 該当する様式に基づき、届出書を作成
- ハローワークまたは外国人雇用状況届出システムへ提出
- 提出控えを社内で保管・共有
状況に応じた提出対応を整理しておくことが、ミスや法的リスクの回避に直結します。
現場での対応に役立つ実務対応の整理と補足
外国人雇用状況届出書の提出業務は、採用直後の限られた期間内に行う必要があるため、社内での体制整備とフローの明確化が欠かせません。特に複数部署にまたがる業務であるため、誰が何を、いつ、どのように行うかをあらかじめ整理しておくことが、業務の遅延やミス防止につながります。
届出の流れと社内での担当分担の考え方
届出業務を正確かつ迅速に進めるには、人事・総務・現場部門間での役割分担を明確にしておくことが重要です。
基本的な社内フローの一例
- 採用決定時(現場・人事)
- 在留カードの原本確認
- 雇用契約書の締結
- 就労予定の業務内容の最終確認(在留資格との適合性チェック)
- 書類準備(人事・総務)
- 届出様式の選定(ハローワークまたはオンライン提出)
- 必要事項の記載:氏名・在留資格・在留カード番号・雇用形態など
- 雇用保険適用の有無に応じて様式を使い分ける
- 提出・記録管理(人事)
- ハローワークへ書面提出、または外国人雇用状況届出システムでの電子申請
- 提出控えの保存と、社内共有フォルダでの管理
担当者の交代や休暇時にも対応できるよう、業務マニュアルやチェックリストを用意しておくと安心です。
また、外国人の中途採用・短期雇用・アルバイトなどパターンの異なるケースが発生する場合は、雇用形態別に提出フローを分けて管理することも有効です。
外部委託(社労士など)を活用する際の注意点
提出業務の正確性や効率を高める手段として、社会保険労務士など専門家への外部委託を検討する企業も少なくありません。しかし、委託する際には以下の点に留意が必要です。
1. 委託範囲の明確化
- 「届出書の作成のみ」なのか、「提出・管理まで含む」のかを契約時に明記
- 雇用保険手続きや就業規則改定などと混同せず、届出業務に絞った契約が必要
2. 個人情報管理の体制確認
- 在留カードの情報や在留資格など、個人情報の取り扱いに十分な配慮が求められます
- 委託先がプライバシーマークや適切な情報管理体制を有しているか確認
3. 在留資格との適合判断は企業の責任
- 届出自体は社労士が対応しても、在留資格と業務内容の適合性判断は企業責任
- 万が一の不法就労と判断された場合、委託していたとしても企業が行政指導や罰則を受けることがあります
4. 届出状況の定期的な社内チェック
- 全てを任せきりにせず、提出済みの控えや提出履歴を社内で保管し、定期的にレビューする仕組みを整えましょう
外部委託を活用すれば手続きの負担軽減が可能ですが、法的責任は企業側にあるため、連携体制の整備が不可欠です。社内運用と外部委託を適切に組み合わせることで、提出漏れやミスを防ぎ、信頼性の高い運用が可能になります。特に初めて外国人を雇用する企業は、早期にフローを整えることが重要です。
まとめ:外国人雇用状況届出は「義務」と「信頼性」の両立が鍵
外国人労働者を雇用する企業にとって、外国人雇用状況届出書の提出は法的義務であると同時に、適切な雇用管理を行う上での信頼構築の要でもあります。提出時の記載ミスや提出漏れは罰則の対象となり得るため、期限や様式の正確な把握が不可欠です。
また、ケースごとの対応や社内分担の整理、社労士など外部委託の活用も実務上有効です。制度の目的と企業の責任を正しく理解し、法令遵守と外国人材への適正な対応を両立させることが、持続可能な人材活用と企業信頼の向上につながります。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/