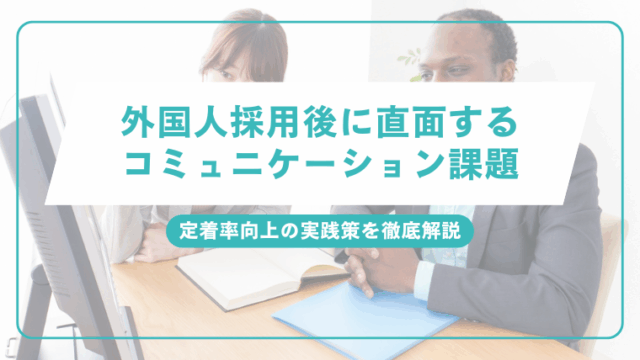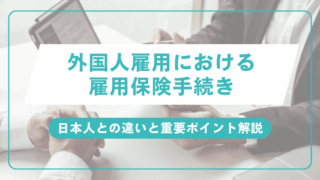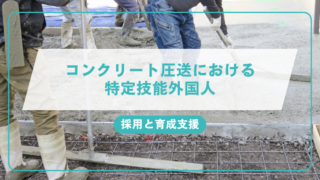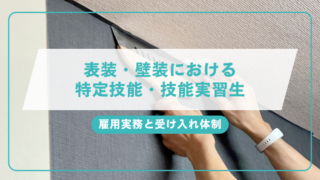外国人を採用する際には、在留資格の要件や労働条件の明確化といった 作成時の注意点をしっかり押さえた雇用契約書の整備が必要です。契約書は、就労ビザ取得 や労使トラブルの回避に役立つだけでなく、外国人本人にとっても働く環境の 安心材料 となります。雇用契約書は義務ではありませんが、実務上は必要不可欠な書類として扱われる場面が多く、内容の精度が企業の信頼にも直結します。
本記事では、契約書作成時に企業が注意すべきポイントや実務対応、労働条件通知書との違いをわかりやすく解説し、法的リスクを回避しながら、実務に即した外国人採用を後押しします。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人雇用における契約書の役割と法的な位置づけ
労働条件の明示義務と雇用契約書の違い
労働基準法により、企業は労働者に対し、労働条件通知書によって雇用条件を明示する義務があります。これは日本人・外国人を問わず適用され、雇用前に書面・FAX・メール・SNS等で交付することが法律で定められています。
一方、雇用契約書は法的義務ではありませんが、労使双方の合意内容を証明する手段として、特に外国人雇用では重要性が高まります。実務上は、通知書と契約書を併用するケースが多く、両者の役割を理解して使い分けることが重要です。
通知書は一方向的な「明示」、契約書は双方の「合意」の証拠という違いがあります。外国人採用では、母国語での説明や翻訳対応を含め、十分な理解と合意形成を図ることが求められます。
外国人雇用における契約書作成の重要性
外国人労働者を受け入れる企業にとって、契約書の役割は単に「労働条件を記録するためのもの」ではありません。言語・文化・法制度の違いから生じる誤解やトラブルを未然に防ぐための法的・実務的な土台として極めて重要です。
特に、以下のような理由から、契約書の作成は強く推奨されます。
- 在留資格審査に必要な証拠資料となる(例:業務内容が資格の範囲内かを判断)
- 外国人本人に対する労働条件の理解を促進できる
- 口頭契約による行き違いや不当解雇の防止につながる
- 契約内容の変更や更新履歴を明確に残せる
加えて、契約書は日本語だけでなく、本人が理解できる言語でも作成・説明することが望ましいとされています。実際、多くの企業では日本語と英語やベトナム語などを併記した雇用契約書を作成しています。
このように、外国人労働者の受け入れにおいては、法的整合性だけでなく、信頼構築や人材定着を見据えた視点からも、契約書の整備が必須となるのです。
雇用契約書と労働条件通知書の違いを正しく理解する
労働条件通知書の交付が義務とされる理由
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、企業が労働者に対して必ず書面で交付しなければならない文書です。これは、日本人・外国人を問わず、労働契約を締結する際に必要な義務であり、雇用開始前に交付しなければ法律違反となる場合もあります。
記載が義務付けられている主な項目は以下のとおりです。
- 契約期間(有期/無期)
- 就業場所・業務内容
- 始業・終業時刻、所定労働時間、休憩・休日
- 賃金の決定方法、支払い方法、締切・支払日
- 解雇・退職に関する事項 など
これらの内容は、日本語でかつ書面による明示が原則です。外国人労働者に交付する場合も、本人が理解できるように翻訳や説明資料を添付する配慮が求められます。厚生労働省では、英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語などの多言語版の労働条件通知書の様式を提供しており、実務での活用が推奨されています。
両方を使い分ける実務的なポイント
労働条件通知書と雇用契約書は似ているようで異なる性質を持っています。それぞれの違いと、実務上どう使い分けるべきかを理解しておくことが、外国人雇用における誤解やトラブルの防止につながります。
| 項目 | 労働条件通知書 | 雇用契約書 |
| 性質 | 労働条件の通知義務 | 労働契約の証拠・合意文書 |
| 作成義務 | 法律上義務あり | 義務ではないが実務上重要 |
| 説明方法 | 使用者から労働者へ一方的に交付 | 双方署名により契約成立 |
| 法的効力 | 労働条件の確認・証明に使われる | 契約内容の法的証明になる |
| 言語対応 | 原則日本語(翻訳推奨) | 日本語+母国語併記が望ましい |
多くの企業では、労働条件通知書を交付した上で、雇用契約書にも署名・捺印を行い、両方を保管する運用を取っています。これにより、労働条件の明示義務を果たしつつ、在留資格の取得や将来的なトラブル対応にも備えることが可能です。
特に外国人雇用においては、口頭での説明や翻訳のみでは証拠能力が弱いため、書面の整備が重要となります。両者を使い分けることで、法的にも実務的にも抜け漏れのない採用体制を整えることができるのです。
記載すべき必須項目と在留資格との整合性
外国人雇用において雇用契約書を作成する際には、労働基準法で定められた必須項目に加えて、在留資格に適合した記載が求められます。ここでは、契約書に必ず盛り込むべき項目と、在留資格と整合性を取る際の注意点を整理します。
雇用期間・業務内容・労働時間など基本情報の明示
雇用契約書には、以下のような基本的かつ必須の労働条件を明確に記載する必要があります。
雇用期間
期間の定めがあるかどうかを明記し、在留資格の有効期限との整合性をとる必要があります。たとえば、在留資格が1年の場合、契約期間がそれを超える場合には更新可能性を示しておくのが適切です。
業務内容
在留資格に基づいた業務であることを前提に、できるだけ具体的に記載します(例:「システムエンジニアとしてJavaによる業務アプリ開発を担当」)。
就業場所
主たる勤務地だけでなく、他の可能性がある場合はその旨も記載しておくことで誤解を防ぎます。
労働時間・休憩・休日
始業・終業時刻、所定労働時間、休憩時間、休日の取り扱いを正確に示し、時間外労働の有無や割増賃金の計算方法も併記するのが望ましいです。
賃金と支払方法
基本給、各種手当、支給日、締日、控除項目を明記。外国人労働者にとって日本の給与制度は馴染みがないため、丁寧な記述が重要です。
退職・解雇の条件
退職時の手続き、解雇条件、契約終了の際の処遇についても明示し、トラブル予防につなげます。
在留資格別に注意すべき業務範囲と記載方法
在留資格の種類によって、外国人が日本で従事できる業務の範囲は異なります。契約書の業務内容が在留資格に認められていない職務内容になっている場合、不許可や不法就労に該当する可能性があります。
例:主な就労系在留資格と求められる業務内容
- 技術・人文知識・国際業務:翻訳・通訳、マーケティング、IT開発、会計など。単純作業(接客、清掃等)は不可。
- 特定技能(1号):介護、建設、農業など14分野に限定。業務内容は各分野の基準に準拠。
- 技能実習:技能移転を目的とし、あらかじめ定められた職種・作業内容の範囲内での就労。
契約書においては、在留資格に対応した表現を明記するとともに、「職務内容の変更が発生した場合は事前に本人と協議のうえ文書で同意を得る」などの一文を入れておくと、安全性が高まります。
特に外国人が在留資格を取得または更新する際には、契約書の内容がそのまま審査対象になるため、資格外活動に該当しないよう、業務内容の記述には細心の注意が必要です。
多言語対応と契約内容説明時の注意点
外国人労働者にとって、雇用契約書の内容を正確に理解することは、安心して働くうえで不可欠です。日本語に不慣れな方に対しては、多言語での対応や翻訳の工夫、契約内容の丁寧な説明が求められます。ここでは、実務で押さえておきたい多言語対応のポイントと注意点を紹介します。
母国語併記による誤解防止と翻訳の注意点
雇用契約書は日本語で作成することが原則ですが、本人が十分に理解できるように、母国語併記や翻訳版の用意が強く推奨されます。以下のような対応が実務では効果的です。
- 日本語と英語、ベトナム語、中国語などの2か国語併記(多くの企業で実施)
- 厚生労働省の労働条件通知書の多言語版を参考資料として併用
- 読み合わせ時に通訳を交える、または契約説明動画などを活用
注意点として、自動翻訳(例:Google翻訳)による誤訳は法的トラブルを招く恐れがあるため使用を避けるべきです。誤訳による契約内容の誤認が原因で、労使トラブルに発展した事例も報告されています。法的用語に対応できる専門の翻訳者や、多言語対応に実績のある行政書士の協力を得るのが安全です。
また、外国語版の契約書を用意する場合も、最終的な法的効力を持つのは日本語版であることを明記しておくと安心です。
用語の正確性と説明責任の持ち方
契約書に使用する文言や用語は、外国人にとってわかりにくい専門用語やあいまいな表現を避けることが基本です。具体的には、以下のような配慮が求められます。
- 「みなし残業」「法定外休日」などの制度用語に注釈をつける
- 「就業場所は変更となる可能性がある」など、曖昧な言い回しを具体化する
- 賃金の控除項目(社会保険料、住民税など)は明記し、説明責任を果たす
さらに、契約内容の読み合わせと確認書の署名は、双方の合意を裏付ける非常に重要なプロセスです。形式的な説明で済ませるのではなく、本人の理解度を確認しながら、口頭で丁寧に説明する体制を整えることが信頼構築につながります。
雇用契約書は単なる文書ではなく、雇用関係の土台を支える重要な法的資料です。多言語対応と説明責任を徹底することが、企業と外国人労働者の良好な関係維持と長期的な雇用安定に貢献します。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
雇用契約書が必要となる具体的な場面と対応方法
外国人雇用においては、雇用契約書の作成が法律上の義務ではない場合でも、実務上必須となる場面が数多く存在します。特に、在留資格に関わる行政手続きでは、契約書の提出が求められることが多いため、あらかじめ準備しておくことが重要です。
就労ビザ申請時の提出書類としての役割
外国人を新たに雇用する場合、在留資格(いわゆる就労ビザ)を取得・変更するためには、入国管理局への申請が必要です。このとき、雇用契約書の写しは、必須の添付書類として扱われます。
たとえば、次のようなケースでは契約書の提出が求められます。
- 在留資格「技術・人文知識・国際業務」などで新規採用を行う場合
- 留学生が卒業後に企業へ就職する際に、在留資格を変更する場合
- 海外からの採用で、在留資格認定証明書を申請する場合
このような場面では、契約書の内容が申請者の学歴・職務内容・在留資格の要件と一致しているかが厳しく審査されます。不整合があると、在留資格の取得が不許可となる可能性があるため、契約書の記載には注意が必要です。
また、外国人本人にも提出が求められるため、本人が理解できる言語での説明と交付もあわせて行うことが望ましい対応です。
外国人採用に重要な就労ビザは「就労ビザとは?種類・申請方法・注意点をわかりやすく解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
在留資格取得・更新に影響するケース
すでに在留資格を持つ外国人を雇用する場合でも、資格の更新時や活動内容変更時に契約書の提出を求められることがあります。そのため、契約内容が変更された際には、必ず契約書を更新し、最新版を保管・共有する体制を整えておくことが求められます。
具体的な場面の例
- 業務内容や勤務地の大幅な変更(例:翻訳業務 → 現場作業)
- 雇用形態の変更(契約社員 → 正社員)
- 給与体系の見直し・賞与の支給開始
これらの変更は、在留資格の範囲外と判断されるリスクがあるため、契約内容と実態の整合性を確保することが重要です。
また、契約終了後も契約書のコピーを一定期間保管することが推奨されており、万が一トラブルが発生した際の証拠資料としても有効です。
外国人採用で起こりうる不成立・不許可への備えと文書対応
外国人を採用する際には、在留資格が取得できない、あるいは契約が成立しないといった想定外の事態も起こり得ます。そうしたケースに備えて、契約書の条文や社内ルールで事前に対応策を明記しておくことがトラブル回避につながります。
条件付き契約条項の書き方と注意点
外国人の採用においては、在留資格の取得を前提とした雇用契約を結ぶケースが一般的です。したがって、契約書には「本契約は在留資格の許可を条件とする」といった条件付き契約条項を盛り込むことが重要です。
具体的な例文
本契約は、従業員が在留資格(技術・人文知識・国際業務等)を取得した場合に限り効力を生じるものとする。許可されなかった場合、本契約は効力を持たないものとする。
このような条文を記載することで、万が一、在留資格が不許可となっても契約が自動的に無効となる仕組みが明確になります。また、外国人本人にもこの点を事前に説明し、不許可時の対応について合意を得ておくことが信頼関係を損なわないポイントです。
契約発効の時期(例:在留カード交付日以降など)も明確にし、雇用開始前の就労が発生しないよう配慮する必要があります。
採用取消・契約解除のトラブル回避策
採用内定後、在留資格が取得できなかった場合や、本人の事情により契約が履行されない場合、採用取消や契約解除の対応が必要になります。ここで重要なのは、その過程が適正であることを証明できる記録や書類が整備されていることです。
対応のポイント
- 条件付き内定通知書を交付し、「在留資格取得を前提とする」旨を記載する
- 契約が無効になった場合の手続きと通知方法を定める(例:文書による通知)
- トラブルを防ぐため、取消理由や連絡履歴を文書で記録・保管しておく
また、契約解除が本人の責めに帰すものではない場合(例:不許可)には、生活費や渡航費の一部をサポートする措置を検討する企業もあります。このような配慮は企業の信頼性向上にもつながります。
採用から入社に至るまでにはさまざまな不確定要素がありますが、文書による記録と合意形成を丁寧に行うことで、法的・実務的なリスクを最小限に抑えることができます。
活用できる参考資料とサンプルの入手方法
外国人雇用契約書を作成するにあたっては、公的機関や専門団体が提供する参考資料や雛形(サンプル)を活用することで、漏れやミスを防ぎ、効率的な書類作成が可能になります。ここでは、特に実務で役立つ情報源と注意点を紹介します。
厚生労働省の労働条件通知書モデルの使い方
厚生労働省では、外国人労働者向けに多言語対応の「労働条件通知書」のモデル様式を公開しています。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語などに対応しており、外国人本人への説明や、理解促進のための資料として非常に有効です。
利用のポイント
- 日本語と外国語が併記された形式で、外国人が内容を視覚的に理解しやすい
- 法定記載事項が網羅されているため、最低限の確認項目のチェックに便利
- Word形式のテンプレートもあり、自社の契約条件に応じて編集可能
ただし、あくまで「通知書」であり、「契約書」として使用する場合は合意文言の追加や署名欄の整備が必要です。労使双方の同意を前提とした契約書として使うには調整が求められる点に注意しましょう。
民間団体が提供する契約書雛形の活用と注意点
自治体、監理団体、外国人雇用支援団体なども、外国人雇用に特化した契約書のサンプルや作成支援マニュアルを提供している場合があります。特に以下のような場面では参考になります。
- 技能実習制度や特定技能制度における契約書(例:技能実習計画に基づく契約書)
- 中小企業向けの外国人雇用導入マニュアル
- 業種別の契約書雛形(例:建設業・介護業・外食業)
注意点として、これらの資料は業種や制度に特化したものが多く、汎用的な契約書とは異なる仕様になっていることがあるため、使用前に必ず自社の状況に適合しているか確認する必要があります。
また、更新されていない古い雛形を流用すると、法改正に対応していない内容が含まれている可能性もあるため、出典の信頼性と更新日付も確認しましょう。
これらの資料を参考にしながらも、最終的には自社の雇用形態・業務内容・在留資格の種類に応じたカスタマイズが必須です。必要に応じて、社会保険労務士や行政書士などの専門家の助言を受ける体制も検討すると安心です。
まとめ:適切な契約書作成が外国人雇用成功の鍵
外国人雇用では、在留資格に適合した雇用契約書の作成と、労働条件通知書の交付が極めて重要です。業務内容や労働時間、給与などを明記し、就労ビザ取得や契約トラブル回避に備えることが求められます。母国語対応や条件付き契約の整備なども含め、丁寧な書面対応が信頼関係と定着促進の鍵となります。
加えて、厚生労働省のモデル様式や専門機関の資料を活用し、実務に即した契約書を整備することが、外国人材の安心と企業側の法的リスク軽減の両立につながります。将来の雇用継続を見据え、契約書の整備をしっかり行いましょう。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/