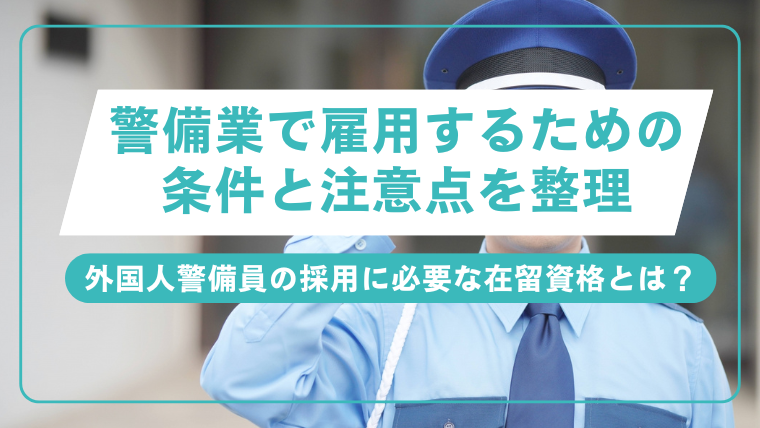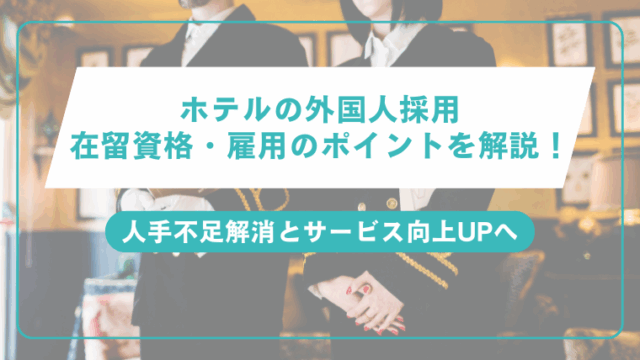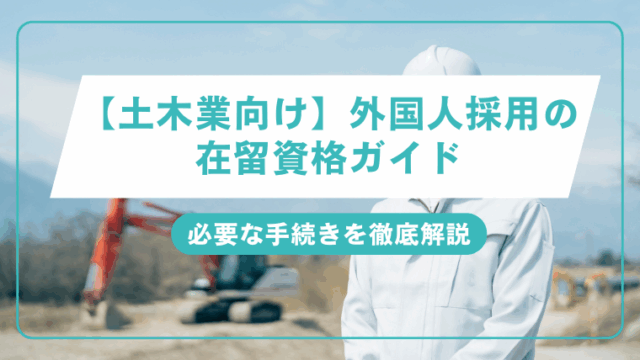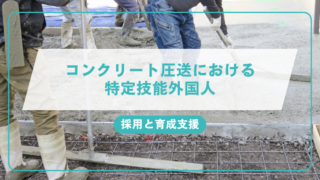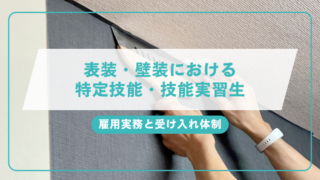外国人を警備員として採用したいと考える企業が増えていますが、在留資格や警備業法など、越えるべきハードルも少なくありません。適切な資格を持たないまま雇用すると、企業側にも大きなリスクが伴います。この記事では、外国人が警備員として働くために必要な在留資格や注意点、採用時に確認すべきポイントをわかりやすく整理します。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
外国人が警備業務に従事できる在留資格の種類

警備業務は、外国人の在留資格によっては就労が原則認められていない職種です。日本の法律では、「警備業」は単純労働に該当するとされ、多くの就労系ビザの対象外となります。ここでは、外国人が例外的に警備業務に従事できる在留資格について整理します。
身分系の在留資格が中心
日本で警備員として働ける外国人の多くは、以下のような「身分に基づく在留資格」を有しています。
・永住者
・定住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
これらの在留資格を持つ人は、職業に制限がなく、警備業務への従事も可能です。
技能実習や特定技能では警備業は対象外のため、これらの資格では警備員として働くことはできません。
不適合な在留資格の例
以下の在留資格を持つ場合、警備員としての業務には従事できません。
| 在留資格名 | 警備業従事の可否 | 理由 |
| 技能実習 | × | 教育目的のため職種制限あり |
| 特定技能(1号・2号) | × | 警備業は対象職種に含まれない |
| 留学 | ×(アルバイト含む) | 資格外活動でも警備は認められていない |
| 技術・人文知識・国際業務 | × | 警備は活動内容に含まれない |
留学生の資格外活動(アルバイト)でも、警備業への従事は明確に禁止されています。仮に採用した場合、企業・外国人双方に処罰リスクが生じます。
外国人警備員の採用に関する警備業法の制約と企業の責任
外国人を警備員として雇用する場合、警備業法や出入国管理法を同時に遵守する必要があります。企業には日本人の採用時以上に、法的確認や慎重な判断が求められます。
警備業法における外国人雇用の制限
警備業法では、以下に該当する場合は警備員としての従事が禁止されています。
・満18歳未満
・破産して復権していない
・禁固以上の刑の前科が5年以内にある
・薬物・アルコール依存の履歴がある
・暴力団関係者等の反社会的勢力との関係がある
・日本語での意思疎通が困難な場合
特に重要なのが「日本語能力」と「犯罪歴の有無」。警備業務では緊急時の対応や報告が必須であるため、一定水準以上の日本語理解力が求められます。
企業側に課される法的義務
外国人を警備員として採用する企業には、以下のような確認・管理責任があります。
・在留カードの原本確認と有効期限管理
・在留資格の種類・活動内容の一致確認
・就労可能かどうかの在留資格の範囲確認
・雇用時の届出(外国人雇用状況の届出)
・必要書類の整備・保管(契約書・指導記録など)
採用後のトラブル回避のために
・定期的な在留資格・期限の確認体制を構築する
・外国人に対する業務マナーや緊急時対応の研修を実施
・通訳や指導者の配置により現場理解をサポート
・警備業法の改正や法的ガイドラインに継続的に対応
企業が制度を誤認したまま雇用を進めると、業務停止や罰則の対象となることもあります。雇用前に行政書士など専門家への相談も有効です。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
採用時に確認すべき必要書類と就労可否の判断ポイント
外国人警備員を採用する際は、在留カードの確認だけでなく、関連する書類全体から「働ける資格かどうか」を見極める必要があります。判断を誤ると不法就労助長罪などのリスクもあるため、慎重な確認が不可欠です。
採用前に確認すべき主要書類
外国人労働者の採用前に企業側が確認すべき書類は、以下の通りです。
| 書類名 | 内容 | チェックポイント |
| 在留カード | 在留資格・期間などが記載 | 就労可能な資格か、期間が有効か |
| パスポート | 入国・在留資格変更・更新履歴など | 不備や偽造がないか |
| 履歴書(日本語) | 学歴・職歴・連絡先等 | 日本語能力の確認にも有効 |
| 健康診断書(任意) | 業務遂行に支障がないか確認 | アルコール・薬物依存の有無等 |
| 資格証明(あれば) | 日本語検定、警備講習修了証など | 実務能力や意思疎通力の確認に有効 |
在留カードのコピーだけでは不十分。原本確認を行い、その内容が実際の業務内容と一致しているかまで確認しましょう。
外国人採用時の在留カードについて「外国人採用時の在留カードチェック完全ガイド!確認方法と偽造対策を徹底解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
在留資格の種類ごとの可否判断
| 在留資格 | 警備員としての就労 | コメント |
| 特定技能1号 | × | 警備業は対象職種外 |
| 技能実習 | × | 警備業での実習は認められていない |
| 技術・人文知識・国際業務 | × | 警備業務は該当しない |
| 永住者・日本人の配偶者等・定住者 | ○ | 在留資格に制限なし、就労可 |
| 留学・家族滞在 | △ | 原則就労不可。資格外活動許可が必要 |
| 特定活動(46号など) | △ | 個別に判断が必要。原則不可が多い |
警備員として就労できるのは、「身分系在留資格」または永住・定住が基本です。就労資格証明書の取得や資格外活動の範囲確認も大切です。
トラブル防止のための運用ルール
・在留カードと就労資格証明書を常に照合する
・在留期限が近づく前に本人へ更新確認を行う
・外国人本人に「自分のビザで働けるか」説明を求める
・書類提出のタイミングと記録を統一して管理
採用段階で「働けない」人を見逃さない体制づくりが、後のトラブル回避に直結します。
日本語能力と教育体制|警備現場で求められる対応力
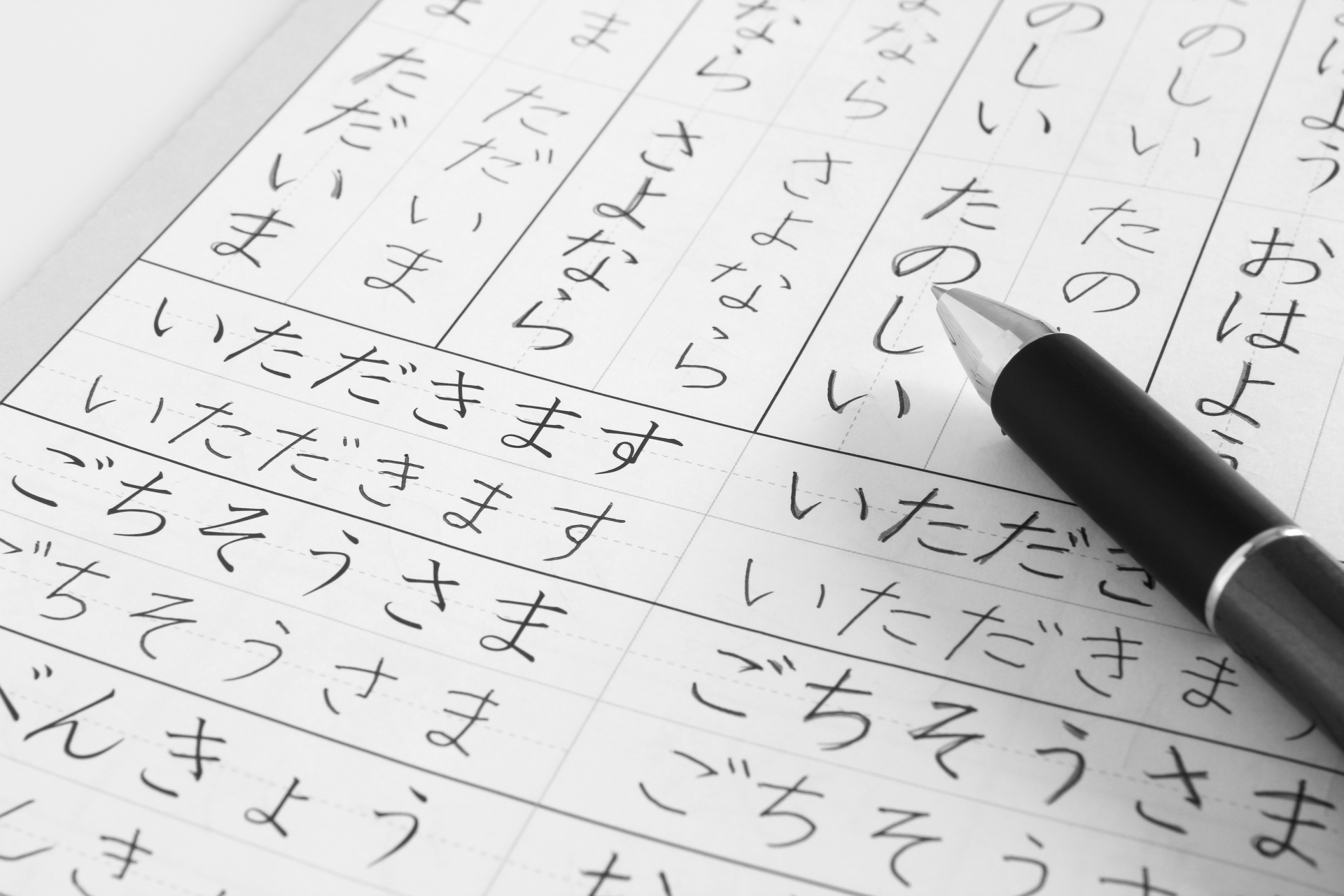
外国人警備員を現場に配属するうえで、日本語での意思疎通ができるかどうかは最重要ポイントです。交通誘導や施設内での案内、トラブル対応など、「瞬時に正確なやり取り」が求められるためです。
なぜ日本語能力が重要なのか
以下のような業務では、高度な日本語理解力と発話力が求められます。
・歩行者・車両への声かけや誘導
・緊急時の通報・報告(110番・119番)
・周辺住民や施設利用者への説明
・現場責任者・仲間との情報共有
・警備業法に基づくマニュアル遵守
「少し話せる」レベルでは不十分です。警備業務では、命に関わる場面も想定されるため、N3レベル以上の日本語力が目安となります。
採用前に確認したい日本語能力の基準
| 確認項目 | 内容 | 推奨水準 |
| 日本語能力試験(JLPT) | 公式な語学力の証明 | N3以上(できればN2) |
| 会話テスト | 面接時に口頭で確認 | 指示の理解と返答ができるか |
| 読解力 | 業務マニュアルを読めるか | 漢字を含む文書の読解力 |
| 報告・連絡・相談スキル | 上司とのやり取りに必要 | 敬語の基本的な使い方含む |
「資格がある」よりも「現場で通じる」かを重視すべきです。現場でのロールプレイングなども採用時に有効です。
外国人警備員向けの教育体制を整える
外国人警備員が戦力化するには、事前教育と継続支援の両方が欠かせません。
教育の工夫例
・警備業法・マナー・報告ルールをやさしい日本語で解説
・視覚教材(図・写真・動画)の活用
・母語が近い先輩社員とのOJTペア制度
・翻訳アプリや辞書アプリの使用許可
・日本語に加えてジェスチャーの活用を習慣化
継続支援の工夫
・配属後1~2ヶ月は定期面談を実施
・苦情やクレーム発生時の振り返り研修
・キャリアアップ支援(例:指導教育責任者補助)
・外国人向け講習会・生活支援との連携
「配属したら終わり」ではなく、定着と成長を見据えた支援が、企業全体の安全性を高めます。
外国人採用における日本語力向上の社内教育などについては「外国人採用における日本語レベルと教育支援|業務定着に必要な確認ポイントと対策を解説」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
外国人採用で警備会社が気をつけたいリスクと対策
外国人警備員を採用する際、在留資格の確認以外にも、現場で発生し得るリスクへの備えが不可欠です。「知らなかった」では済まされない責任が企業にあることを踏まえて、リスクとその対策を整理します。
採用・配属前に注意すべきリスク
| リスクの種類 | 内容 | 推奨対策 |
| 資格不適合 | 警備業務に従事できない在留資格での雇用 | 在留カードの原本確認・弁護士等の監修 |
| 虚偽申告 | 学歴・経験・在留資格の虚偽申告 | 出入国在留管理庁での確認、面接の突合せ |
| 日本語力不足 | 現場で意思疎通が困難 | 採用前の日本語面接+実技テスト |
| 犯罪歴・風評 | 元反社会勢力・暴力団関係・薬物歴 | 身元保証・警察提出の身辺調査書類を徹底 |
| 文化的ミスマッチ | 現場慣習や働き方に適応できない | 文化理解研修・日本人従業員との橋渡し支援 |
警備業法は「性格が誠実で、破産や禁固歴がない者」に限定されるため、外国籍であっても過去の経歴チェックは極めて重要です。
就業後の主なトラブルとその対処
- 勤務態度や報連相の齟齬
→ 指導責任者との週次面談を設ける - 不法就労の疑い(ビザ切れ)
→ 在留期限の社内管理システムを構築 - 言語ストレスによる離職
→ 日本語・生活支援の専門窓口と提携 - 住居・健康保険の未整備による社会不安
→ 初期支援として住宅紹介・社保加入手続きのサポートを行う
コンプライアンス意識の浸透
外国人を雇用するということは、企業が「雇用主責任の範囲を明確に認識しているか」が問われる時代です。
・在留カードの偽造確認(ICチップ確認含む)
・雇用契約書・労働条件通知書の多言語対応
・警備業法と入管法の両立(配属可能業務の遵守)
・研修記録・業務日報の保存によるトラブル時の証拠保全
形式的な確認ではなく「実務的なリスク管理」が、企業の信頼を守ります。
外国人採用時の雇用契約書について「外国人採用の雇用契約書ガイド|作成時の重要ポイント、注意点を徹底解説!」で詳しく解説していますので合わせてご閲覧下さい。
まとめ
外国人を警備員として採用するには、就労可能な在留資格の確認と警備業法上の要件の理解が不可欠です。特定技能や技能実習では警備業務は不可となるため、「永住者」や「定住者」などの身分系在留資格の確認が重要なポイントとなります。また、採用後も日本語能力や文化的背景に配慮した教育・支援が求められます。適切な手続きと社内体制の整備により、外国人警備員との円滑な協働が実現します。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/