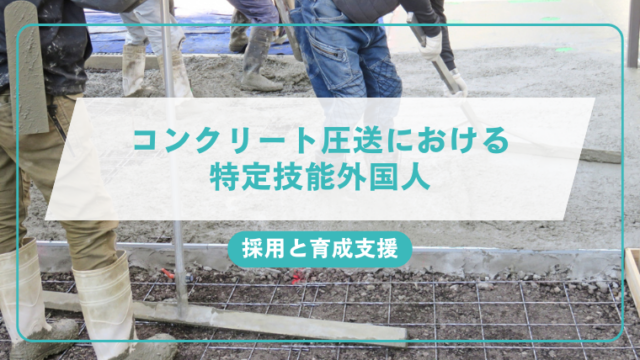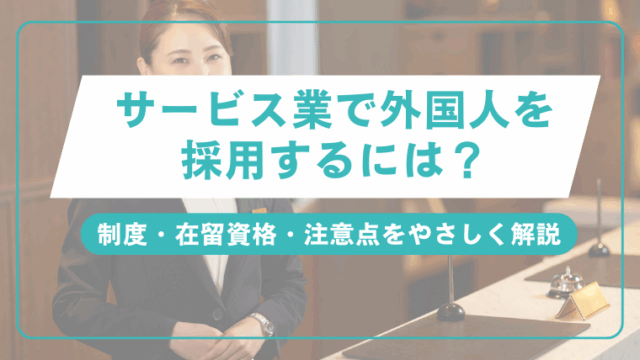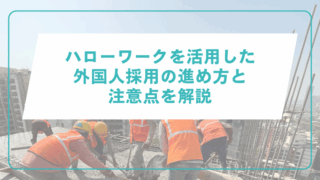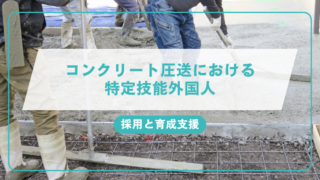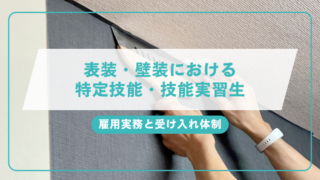警備業界の人手不足を背景に、外国人材の採用を検討する企業も増えています。
しかし、警備員として外国人を雇用するには、在留資格や法的な制限を正しく理解しておく必要があります。本記事では、外国人の採用が認められる条件や注意点、雇用可能な資格の種類を実務目線で解説します。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
警備業で外国人を採用できるのか

外国人の採用が進むなか、警備業界では「外国人を警備員として雇ってよいのか?」という疑問が多く寄せられます。実は、警備員という職種は他業種と比べても法的な制限が非常に強い分野です。以下では、その根拠となる法律と、採用が認められるケースを整理します。
警備業法が定める「制限」とは
警備員を雇用するには、「警備業法」という法律に従う必要があります。この法律では、以下のように外国籍の人物に対して明確な制限が設けられています。
主な制限内容(抜粋)
・外国人が在留資格を持たない場合、警備員としての登録はできない
・警備業務に就くには「欠格事由」に該当しないことが必要
・欠格事由のひとつに「日本国籍を有しない者で、適法な在留資格を持たない者」が含まれる
つまり、すべての外国人が警備員になれるわけではなく、法律で限定的に許可されているのみなのです。
就労が可能な在留資格について
外国人が警備業に従事するには、以下のような在留資格を持っている必要があります。
警備員としての採用が現実的な在留資格
・永住者:就労制限なしで、日本人と同等に働ける
・日本人の配偶者等:業種制限なし
・定住者:職種に制限なし(法的に就労可能)
・永住者の配偶者等:上記と同様に制限なし
上記の在留資格であれば、法的に警備員として働くことは可能です。逆に、技能実習生や留学生、特定技能1号などの資格では、警備業務は認められていません。
外国人警備員を採用する際の実務的なチェックポイント
在留資格がクリアできたとしても、実際の採用にあたっては別の現場的な課題も存在します。
ここでは、外国人警備員を採用・配置する際に企業が押さえておくべき重要な実務ポイントを紹介します。
日本語能力とコミュニケーションの壁
警備業務は、人と接する機会が非常に多い職種です。現場での巡回や受付、施設管理、イベント警備などでは、日本語でのやりとりが必須です。
必要な日本語能力のレベル感
| 活動内容 | 必要な日本語スキルの目安 |
| 受付案内 | 日常会話〜ビジネス初級レベル(N3以上) |
| 施設巡回 | 指示理解と報告スキル(N4〜N3) |
| 緊急時対応 | 高い読解力・迅速な理解力(N2以上が望ましい) |
特に高齢者や子どもと接する場面では、言葉づかいの丁寧さも求められます。そのため、日本語能力試験(JLPT)などの指標を活用して判断するのが一般的です。
研修制度とマナー教育の整備
外国人に限らず、警備員には入社時の法定研修(新任教育20時間以上)が義務付けられています。外国人採用の場合、以下の点を意識する必要があります。
・言葉の壁を考慮した研修資料の準備(やさしい日本語・視覚資料など)
・日本の礼儀作法や職業倫理の共有
・実技とロールプレイを組み合わせた研修
警備業務では、制服の着こなしや立ち居振る舞いも「会社の顔」として見られます。そのため、日本人スタッフと同等以上のマナー教育が必要です。
不測の事態に備えた体制づくり
外国人警備員の配置に際しては、緊急対応の可否やトラブル時の通報体制も事前に検討する必要があります。
・不審者対応や緊急通報を適切にこなせるか
・同行・補助スタッフを配置する体制があるか
・日本語でのマニュアルを理解できているか
安全性を損なわない範囲での業務配置を心がけ、現場との擦り合わせを行いましょう。
外国人警備員採用のメリットと導入企業の実例
外国人の警備員雇用は、制度的制約もある一方で、多くの企業が可能性を見出しています。
このセクションでは、外国人採用による実際のメリットや、導入事例の傾向を紹介します。
外国人警備員を採用するメリット
警備業界では慢性的な人手不足が続いており、特に以下のような分野で外国人の人材活用が注目されています。
・深夜や早朝の時間帯に対応できる柔軟性
・外国語(英語・中国語)での対応力
・若年層の労働力確保による高齢化対策
特に外国人観光客が多い施設・空港・イベントなどでは、多言語対応できる警備員の配置が顧客満足度の向上に直結します。
また、永住者や日本人の配偶者など、就労制限がない外国人材を活用することで、採用コストや定着率の安定にもつながるケースがあります。
採用企業の傾向と導入事例
実際に外国人警備員を導入している企業には、以下のような傾向が見られます。
・都市部を中心に展開する警備会社(駅・商業施設の巡回)
・イベント警備やスポーツ会場の警備業者
・宿泊施設・観光案内所と連携する施設警備会社
たとえば、東京都内のある大手警備会社では、永住者資格を持つネパール人スタッフを受付案内に配置。
日本語・英語・ネパール語の三言語対応で、インバウンド対応に高い評価を得ています。
また、関西の中堅企業では、日本人の配偶者として来日した外国人スタッフを夜間巡回業務に採用し、定着率の向上と人員配置の柔軟化を実現しています。
在留資格別 警備職 就労可否一覧
| 在留資格 | 警備職 就労可否 | 詳細 |
| 永住者 | ◎ | 就労制限なし。
警備員として勤務可能。 |
| 日本人の配偶者等 | ◎ | 同上 |
| 永住者の配偶者等 | ◎ | 同上 |
| 定住者 | ◎ | 同上 |
| 留学(資格外活動許可あり) | △(条件付き) | 原則就労不可。資格外活動許可で週28時間以内で勤務可。 |
| 家族滞在(資格外活動許可あり) | △(条件付き) | 原則就労不可。資格外活動許可があれば週28時間以内で勤務可。 |
| 文化活動(資格外活動許可あり) | △(条件付き) | 原則就労不可。資格外活動許可があれば週28時間以内で勤務可。 |
| 技術・人文知識・国際業務 | × | 警備業は対象外。 |
| 特定技能 | × | 警備業は対象外。 |
| 技能実習 | × | 警備業は対象外。 |

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/
警備業界が外国人採用で注意すべきリスクと法的制限

外国人を警備員として採用する際には、在留資格だけでなく、警備業法や関係法令に基づく制限やリスクも十分に理解する必要があります。特に「警備業務」は安全と密接に関わる業務であるため、就労の可否や条件は他職種以上に厳格です。
警備業務が制限される主な理由
警備業務に外国人が従事することには、以下のような背景から制限がかかっています。
・機密性や安全保障に関わる業務が含まれるため
・事件・事故時の対応や報告に高度な日本語力が求められるため
・警備業法第14条の「欠格事由」に該当する可能性があるため
とくに警備業法では、従業員に「一定の在留資格を持ち、欠格事由に該当しない者」を求めています。これは、過去に犯罪歴がある、破産者で復権していない、日本語による円滑なコミュニケーションが困難などの場合に該当することがあります。
採用前に企業が確認すべきポイント
外国人警備員の雇用を検討する場合、企業側での確認と整備が必須です。以下の点は特に重要です。
・ビザと在留カードの有効性の確認
・就労可能な在留資格かどうかのチェック
・警備業法上の欠格事由への該当有無の確認
・警備業登録票の記載と整合性の確認
・研修体制や通訳対応の有無の整備
こうした確認を怠ると、雇用主が不法就労助長罪に問われる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。
現場で起こりうるリスクと対処
警備の現場では、予測不能な事態への即時対応や、来訪者・住民とのやりとりが日常的に発生します。以下のようなリスクと対処が必要です。
| リスク例 | 対応策 |
| 日本語での緊急通報や報告が遅れる | 日本語能力の確認と訓練、簡易マニュアル整備 |
| 法令違反による事業停止や罰則 | 管理者による在留資格・研修記録の定期確認 |
| 業務内容の誤解によるトラブル | 業務マニュアルの翻訳、日常会話レベルの日本語研修 |
警備業務に対する理解不足がトラブルの要因となることも多いため、事前研修と実地指導は欠かせません。
外国人採用が警備業にもたらすメリットと期待できる効果
警備業界における人材不足は深刻化しており、とくに若年層の担い手不足や高齢化が大きな課題となっています。こうした中、外国人採用がもたらすメリットは少なくありません。法令に準拠したうえで適切に採用すれば、現場の活性化や企業成長にもつながります。
若年人材の確保による現場の安定化
警備業界は平均年齢が高く、体力や反応速度が求められる現場では慢性的な人手不足が課題です。そこで、比較的若年層の外国人材の活用が効果的です。
・夜間の施設警備やイベント警備など体力を要する業務への対応力
・早朝・深夜など日本人が敬遠しがちなシフトへの柔軟な対応
・若手中心による現場の活気向上
とくに永住者・定住者など在留制限のない人材であれば、長期的に安定して働ける点も企業にとっては大きな利点です。
多言語対応・多様性のある接客力
訪日外国人の増加や国際的なイベントの開催に伴い、英語や中国語など外国語対応が可能な警備員の需要も高まっています。
・駅構内・空港・観光施設での案内補助
・商業施設での外国人顧客への対応
・多国籍コミュニティ内での警備・巡回業務
多様な言語と文化背景を持つ人材が加わることで、サービスの幅が広がり、利用者の満足度向上にも寄与します。
高い意欲と責任感を持つ人材が多い
日本で就労すること自体に目的意識を持つ外国人労働者は、総じて仕事に対する姿勢が真面目です。以下のような傾向が見られます。
・就労ビザや在留継続のために高い勤労意欲を維持
・警備研修やマナー教育にも真摯に取り組む姿勢
・長期就業やキャリアアップを前提とした雇用契約への関心
企業側が正しい支援体制を整備することで、企業と外国人双方にとって有益な雇用関係を築くことが可能です。
まとめ
外国人を警備員として採用するには、在留資格や警備業法に基づいた正確な知識と、採用後のサポート体制が重要です。永住者や定住者のように在留活動の制限がない人材の活用であれば、法的なリスクを避けつつ人材確保が可能になります。多言語対応や若年層の雇用といったメリットもある一方、在留資格の確認・法令順守・研修制度など、企業側の準備が成否を分けます。人手不足の時代だからこそ、正しい方法で外国人材と向き合い、戦力として育てることが求められます。

外国人材ナビは「外国人採用」をサポートいたします!外国人の受入れをご検討中の企業様はお気軽にご相談下さい。
\外国人の受け入れ方法・費用・必要書類等お気軽に相談下さい/